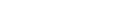三人の遁世者達〔平等・千観・増賀〕
玄賓僧都に続いて『発心集』に載せられているこの三人の遁世者達も、またいずれも名利の俗心を離れたその高潔な行跡の故に、後世の人達に崇められた名僧である。現代には地位や名誉のある所謂(いわゆる)「高僧」はいても、このような名利を超脱した真の名僧がいないのは、誠に惜しいことである。
平等供奉(びょうどうぐぶ)
先の玄賓僧都に次いで『発心集』に載せられているのが、平等供奉であり、その遁世(とんせい)から往生までの経緯が述べられている。生没年や詳伝は不明であるが、「供奉(ぐぶ)」とは「内供奉」の略で、宮中の内道場に仕えて読師(とくし)などを務めた高僧のことであるという。鴨長明の記述は次の如くである。(長明の頃から)さほど遠からぬ昔のこと、比叡山に平等供奉という尊いお方がおられた。天台宗と真言宗の高僧であった。
あるとき、便所に入っていた折りのこと、にわかにはかない無常を痛感する気持ちが起り、「どうしてこのようにはかない世であるのに、名利にのみ束縛されて、執着すべきでないわが身をいとしく思って、空(むな)しく日々を送っているのであろうか」と思うと、過ぎ去った日々もくやしく、何年も住んだ栖(すみか)も嫌になったので、もう戻ってくるという気持ちにはならなかった。下着姿で下駄を履いたままの格好で、衣などを着たりすることもなく、何処(どこ)へともなく出奔(しゅっぽん)して、比叡山から都に出るための、通称「雲母坂(きららざか)」と呼ばれる西の坂を経て京の方へ下っていった。
どこに身を落ち着けようという気もなかったので、足の向くがままに任せて船着き場のある淀の方へ放浪して行き、下り船があったので乗ろうとした。供奉の顔つきなどが尋常ではなかったので、船頭は怪(あや)しく思い乗船を承知しなかったが、必死になって頼み込むので、乗せることにした。
「一体、どういうわけで、どこへ行こうとされるのか」と船頭が問うと、「別段これといった目的もなければ、目指していくような当てもない。ただ、どこへなりとあなた達がいらっしゃる方へ参ろうと思う」と答えたので、一同は、「わけの分からぬ話しだ」と首をひねっていたが、粗野な船頭達も情がなくもなかったので、たまたまその船の行き先のままに、伊予の国(今の愛媛県)に到着した。
さて、供奉はこの伊予の国をあちこちさまよい歩いて、乞食(こつじき、物乞いのこと)をして日を送っていたので、その国の人々は彼のことを「門乞食(かどこつじき)」(門口に立って物乞いをする者)と名付けた。
比叡山の坊では、「ちょっとお出かけになってからその後、いつまで経っても戻ってこられないとはおかしいことだ」などと言い合っていたが、こんなことになっているとは、どうして想像できたであろうか。「もしかして何かわけがあるのだろう」などと言っているうちに、その日は暮れ、夜も明けてしまった。一同は驚いて探し回ったが、一向に見つけることはできなかった。あれこれ言っても仕方がないので、もっぱら供奉が死去したものと仮定して、泣く泣く、故人を弔う仏事を行い合ったのである。
この間、伊予の国の守(かみ、長官)であった人は、供奉の弟子の浄真阿闍梨(じょうじんあじゃり)という人を長年懇意にして祈祷などをしてもらっていたが、京から国へ下るというので、「長い道程ですので、貴僧に同道して頂ければ心強いことでしょう」と言って、同伴して京から下ってきた。
門乞食の平等供奉は、そんなことは知らずに、伊予守(いよのかみ)の館(やかた)の内へ入って行った。物乞いをする間に、童(わらべ)らは大勢で後ろに立って笑い罵(ののし)った。その場に居合わせた伊予の国の住民達が、「何という異様な格好だ。ここから出ていけ」と激しく叱りつけるのを、この阿闍梨は哀れに思い、物などを取らせようと思って自分の近くに呼んだ。
恐れ恐れ縁側へやって来たのを見れば、人の姿にも見えないほど痩(や)せ衰え、あちこちからボロが垂れ下がった綴(つづり、切れを継ぎ合わせて仕立てた着物)のみを身にまとった、まことに見苦しい様であった。
とはいえ、身なりは変貌してはいたが、どこかで見覚えがある様に思い、よくよく思い出せば、我が師であった。何とも悲しくなって、すだれの中から転がるように出て、縁の上に手を取って上がらせた。伊予守を始めありとあらゆる人は、驚き悲しむあまり、泣く泣く様々に語ったが、供奉は言葉少ないまま、強いて暇を乞うて立ち去ってしまった。
あまりのことに言葉も出ないまま、麻の衣などの物を用意して然るべき処を探索してみたが、どうしても供奉は見つからない。あげくの果てには、国の者達に命じて、山林の至らぬところもない位、隅々まで探し回ったが、逢うことはできずに、そのまま行方不明になって、ついに行く末も知られぬままになってしまった。
その後、はるかに時が経ってから、人も通わぬ深山の奥深い清水のある処に「死人がいる」と山の住人が言うのを聞いて、怪訝(けげん)に思い、阿闍梨が探して行って見れば、平等供奉が合掌して西方極楽浄土に向かって往生を祈念しながら亡くなっていた。大層悲しいと同時に貴く感じて、阿闍梨は泣く泣く亡き師の葬儀を執り行なったのである。
ここまで述べて、鴨長明は発心をして遁世した高僧達について次のように総括している。
今も昔も、真実の道心を発(おこ)した人は、このように故郷を離れ、見ず知らずの処で、いさぎよく名利を捨てて死ぬのである。悟りを求めて修行する菩薩が無生忍(むしょうにん)1を得た上でさえ、顔見知りの人の前では神通(じんづう)2を現わすことは難しいと言われている。まして、確かに発心をしたことは尊いとはいえ、不退の位に到らなければ、何かにつけて乱れやすい。故郷に住み、知った人に交わっては、どうして一念の妄念の心を起こさずにはおれようか。
千観内供(せんかんないぐ)
鴨長明は、平等供奉に続いて三井寺(滋賀県大津市にある園城寺の別称)の千観内供(延喜17年〜永観元年、917 – 983)の遁世・往生について述べている。ここでも、多少の解説を加味しながら、長明の記述に即して述べることにしよう。千観内供という人は、智証大師円珍(三井寺の開祖)の系統に属する比類なき智者であった。もとより道心は深かったが、どのように振る舞い、行動すれば良いかなどと思いを定めず、何となく月日を送っていた。或る時、朝廷から法会・講論に招かれての帰り道、京都四条河原で空也(くうや)上人にお目にかかった。上人は、市井(しせい)にあって鉦(かね)などを鳴らして踊りながら阿弥陀の名号を称える「踊り念仏」で有名で、貴賎に尊敬され、浄土思想の普及に測り知れぬ功績を残した人である。
内供は車から下(お)りて上人に対面し、「一体どのようにすれば、来世の安楽が得られるのでしょうか」と伺うと、上人はこれを聞いて、「何を反対のことを言っておられるのか。そのようなことは、この私が御房(ごぼう、僧侶の尊称)などに伺いたいものですのに。私のような至らぬ身では、ただ言う甲斐もなくあちこち迷い歩くだけです。それ以上に何か思いつくようなことはございませぬ」と言ってその場から去ってしまわれようとするのを、内供が袖を捕まえて、なお熱心に尋ねたところ、上人は、「どのような仕方であれ、わが身を捨てれば救われましょう」とだけ言って、袖を引き放ち、足早に行き過ぎてしまわれた。
その時、内供は四条河原で僧侶の装束を脱ぎ代え車に入れて、「ともの者は早くお寺へ帰りなさい。私はこれからよそに行ってしまうつもりなのだ」と言って、全員を返してしまって、自分はただ独りで箕面(みのう、原文では「蓑尾」。大阪府箕面市)という所に籠(こも)ってしまった。
しかしながら、なおそこも気に染まなかったのであろうか、居所を決めかねておられたところ、東の方に金色(こんじき)の雲が立ち上っていたので、その場所を尋ね、形通りの庵(いおり)を結んで、跡を晦(くら)まされたのであるが、それがすなわち現在の金龍寺(こんりゅうじ)というのがそれである。そこで長年修行して遂に往生を遂げられた経緯(いきさつ)は、詳しくその伝記に記(しる)されている。
この内供は、人の夢に千手観音(せんじゅかんのん)の化身として現れたということである。千観という名は、この観音の御名(みな)を省略したものであろう。
鴨長明は千観内供についての一段をそう締めくくっている。内供は生涯念仏を絶やすことはなかったといわれ、そのため「念仏上人」と称(たた)えられたという。
増賀上人(そうがしょうにん)
奈良県桜井市にある多武峰(とうのみね)の増賀(そうが)上人(延喜17年〜長保5年、917 – 1003)。長明は「僧賀」と記しているが、正しい表記に従い、以下「増賀」と記す)は、その奇行と高徳で名高いが、長明は前二者に続いて、この増賀上人の「遁世往生」について述べている。増賀上人は、天台宗比叡山中興の祖といわれる慈惠(じえ)僧正(元三大師良源)の弟子である。幼くして十歳で出家した上人は、徳の高さが人に勝(すぐ)れていたので、「行く末には立派な名僧になられるであろう」と、至る所で人々は賞賛し合った。
しかしながら、上人は心の中では深く俗世を厭(いと)い、名利(みょうり、世間的な名声と現世的な利益)にとらわれず、極楽に生まれることだけを人知れず願っておられた。納得のゆく道心がなかなか発(おこ)らぬことだけを願って、根本中堂(比叡山延暦寺の本堂)に千夜お参りし、毎夜千回の礼拝(らいはい)をして道心が生まれるのをお祈り申し上げた。
始めは、礼拝するたびに声など立てることはなかったが、六、七百夜頃になると、「つきたまえ、つきたまえ」と人に知られぬほどのひそかな声を出して礼拝したので、その声を聞いた人は、「このお坊さんは一体何事を祈って、天狗(てんぐ、妖怪の一種)がつくようにというのか」などと、怪しんだり笑ったりした。しかし、参拝が千回の終わり近くになって、「道心がつきますように」とはっきり聞こえるようになったので、人々は、「何という立派なことだ」などと言い合った。
こうして千夜が達成して後、前世からの因縁であったのか、上人は世を厭う心がますます深くなったので、「何とかしてわが身を空しくしてしまおう」と機会を待っていたが、ある時、内論議といって、大極殿において天皇の目前で正月十四日に行われる、経文の内容を高僧達に論議させる催しがあった。
一定の論議が終了したので、供養のために貴人達の食べ物の残りを庭に投げ捨てると、乞食達が方々に集まって、争い合って食べるという習わしであったが、増賀上人はにわかにその場に居合わせた僧侶の中から走り出て、これを取って喰らった。
これを見た人が「この禅師は物に狂ったのか」と大声で騒ぐのを聞いて、上人は、「わしは物に狂っておらぬ。そう言われるお手前方こそ、物に狂っておられるのではないか」と言って、少しも驚くことはなかった。人々が「あきれたことだ」と言い合っていると、これを機会に上人は家の中に立てこもってしまった。その後、大和の国の多武峯というところで、思いのままに修行して年を送ったのである。
その後、上人の尊いことが有名になり、時の后(きさき)の宮が出家される際の戒師(授戒の僧)に召されたので、上人は気が進まなかったが参上して、紫宸殿の欄干の端に寄って、いろんな見苦しいことを語りかけ、役割を果たすことなく退出した。
また、上人は、仏事を行おうとする人のもとへ行く間に、説法の仕方などを道すがら思案したので、「これは名利を思うということだ。魔がつけ入ってきたのだな」と思い、行き着くや否や、どうでも良いことを咎め立てして、施主(供養主)といさかいをして供養の仏事を行うことなく帰ってきた。こうしたやり方は、上人が、人にうとまれて再びこのようなことを頼まれないようにとの思惑からであったと思われる。
また、師であった良源僧正が、帝から与えられた栄誉のお礼言上の折り、増賀上人は先駆の数の中に入って、乾鮭(からざけ)というものを太刀(たち)にぶらさげ、やせこけて見苦しい雌牛に乗り、「屋形つきの牛車の先払いを致しましょう」といって、面白く牛の向きを再三変えて乗り回したので、見物者で怪訝(けげん)に思い驚かぬ者はなかった。
こうして上人は、「名聞(名声)は苦しいものだ。気楽なのは乞食(こつじき)の境涯だけだ」と歌って、車から打ち離れた。僧正も凡人ではなかったので、上人の「われこそ屋形つき牛車の先導を」と言われた声が、僧正の耳には、「悲しいことだ、わが師は悪道に入ろうとしている」と聞こえたので、車の中で、「これも衆生済度のためだ」と答えられたのである。
増賀上人は、臨終の時、まず碁盤を取り寄せて、独り碁を打ち、次に蝶々の形をした泥よけの馬具を取り寄せるように頼んで、これを首にかけて小蝶という舞いの真似(まね)をした。弟子達が怪訝に思い尋ねると、「わしは幼少の頃、この二事を人に諌(いさ)められて、してみたいと思いながらせずじまいに終わったが、それが心に懸かっているので、『あるいは死後に執念を残すことがあるかも知れない』と思って」と言われたということである。
すでに極楽の諸菩薩衆が来迎(らいごう)するのを見て、上人は喜んで歌を詠んだ。「八十余りという老齢に及んで、このような稀な出来事に遭うことのできたことの嬉しさよ」という意味の歌を詠み、亡くなった。
最後に、鴨長明は次のように増賀上人の奇行の本意を結論付けている。
この人の振る舞いは、後世の人達は物狂いというかも知れないが、汚(けが)れた世の中から離れんがための思惑(おもわく)があっただけなので、それにつけても稀な例であると思って、ここに採り上げたのである。
人と交友するしきたりは、身分の高さに応じて低い者を憐れむことであるから、身は他人のものとなり、心は恩愛のために使われる。このことは、この現世の苦しみであるばかりでなく、世間を出離する上で大きな障害である。汚れた俗世間を離れるのでなければ、どうして乱れやすい心を静めることができようか。
『発心集』には、増賀上人が奇行に走るほど極端に名利を厭うようになった経緯(いきさつ)に関しては、何ら述べられてはいない。
しかし、上人に関する説話を集大成した談山神社本の『増賀上人行業記絵巻(上巻・下巻)』には、次のような逸話が述べられている。
前述の如く、京都生まれの上人は、十歳で出家し、比叡山で元三大師慈慧のもとで万縁を杜絶(とぜつ)して、久しく山を下りることなく修行・勉学に励んでいたが、或る時、生家を思う念が生じ、たちまち山を下って生家に至った。
当時、父はすでに死去し、母だけが存命中であり、その生家は壁が壊れ建物は傾くという有様であった。母に見(まみ)えると母は息子である上人に向かって言った。
「お前はすでに仏門に入った身である。この母はお前が生家に戻ってくることなど望んではいない。ただお前が如説(教えの通りに)修行して、早く聖人の位に登り、その道力のお蔭で、父母の私達が共に出離(俗界を離れて涅槃寂静の境地に入ること)することができるようにと願うだけである。それなのに、今のお前は良い衣を着て、召使いまで従えている。私はそれを見て、お前の心が菩提(ぼだい、悟りのこと)にではなく、(出家者がもっとも厭離すべき)名利(みょうり、名誉と利益)にあることが分かる。もし、お前が道からそれて名利を求めて菩提を求めなければ、恐らく両親は出離を得ることができぬばかりか、かえって地獄のくずと成り果ててしまうに違いない」
上人は、母のこの言葉が骨身にしみて大いに恥じ入り、謹んで慈訓(慈愛から発せられた訓戒)の真意を了解した。根本中堂でのかの「道心つきたまえ」という礼拝祈願は、この母の痛烈な訓戒を受けて叡山に帰山してからすぐ後の出来事である。上人にとっては、それ以来、名利を厭離すること恰(あたか)も怨敵に逢うがごとき有様であったに相違ない。上人の奇行の背景には、その母の無上の慈愛が窺(うかが)えるのである。
・「名僧列伝」トップへ..
・このページのトップに戻る..