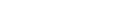臨済禅の公案工夫
公案を用いて「無我の自己」を徹見しようとする臨済禅も、ほとんど公案を数えるだけの形骸化したものに堕しているのが現状である。公案禅をこの窮地から救うと共に、我々自身も真の法悦を得るためには、やはり「根本の一心を明らかにする」という原点に戻るべきである。
禅本来の道
すでに述べたように、儒教・神道・仏教のそれぞれが、無我の根本的境地への到達・長養1の仕方を試みてきた。とはいえ、例えば儒教などにおいては、遺憾ながらその方法が明確に確立されたとは言えない。そのため、訓詁解釈をこととする儒学者はいても、儒教の教えを体現した真の儒者は、すでに幕末で絶え果ててしまったといわれる。
「一方、わが禅門にあっては、見性2して自己心中に大道を明らめるという真実の伝統が、摩訶迦葉(まかかしょう)尊者3以来、歴代の祖師方が着実に受け継いで今日に到っている。」
(今北洪川『禅海一瀾』六丁裏、盛永訳、前掲書44頁)
今北洪川老師(文化十三年〜明治二十五年、1816 – 1892)がそう続けて書かれたのは、文久年間であり、すでに百四十年も前のことである。しかしそれ以来、曹洞宗はもとより臨済宗も次第に衰退の一途を辿っているのは、誰の眼にも明らかであろう。
それゆえ、このホームページの開設を敢行したのも、「無我・至誠の真境涯」を体得する最も端的かつ
直截(ちょくせつ)4な禅の道を、いささかなりともお知らせしたいがためである。
公案禅とは
曹洞禅はさておくとして、臨済禅ではいわゆる「公案」といわれる問題を師家(しけ)から与えられ、それに取り組むことによって「見性成仏」(けんしょうじょうぶつ)の実を挙げることを目指している。公案とはすなわち、歴代の祖師方がそれによって大悟された「機縁」である。師家の室内に参禅して、知解分別(ちげふんべつ)では到底答えることのできぬ公案の解答(これを「見解」〔けんげ〕という)を呈示して、師家と問答することが、俗に「禅問答」と呼ばれるものである。
とはいえ、頭でいくら考えても一向に出る答えではないので、参禅者にとっては参禅の時間はつらいものとなる。
公案工夫のあるべき姿に関しては、無門慧開禅師5が『無門関』6の中の「無字」の評唱で、ご自分の体験に基づいて親切の限りを尽くして述べておられるので、詳しくはそれを参照されたい。
要するに、肝心なことは、公案を頭であれこれ考えることではなくて、公案そのものに成り切ってしまうべく、全身全霊を挙げて、しかも間断無く工夫することである。無字7の公案ならば、坐禅の時だけではなく四六時中・行住坐臥を通じて「無、無、無」と成り切る工夫をして行くのである。
真一文字の鈍工夫
勿論、その際に基本となるのはやはり坐禅における工夫であるのは言うまでもない。我が身を火の塊(かたまり)のようにして気違いと見まがうばかりに、寸暇を惜しんで丹田に気を満たしめ、脊梁骨を伸ばして坐禅しなければならない。しかし、そうであるからといって、坐に執着して動中を嫌うならば、真の三昧境は現前しない。動中を避ける人は、静中の工夫即ち坐禅における三昧発得も不充分な人が多い。工夫三昧の人には元来動中、静中の区別などないはずである。動中で得た定力で坐禅をし、坐禅で錬った定力で動中の工夫をすれば、隙(すき)がなくなり、雪達磨式に工夫が純熟してくる。
とはいえ、四六時中間断無く工夫三昧になることなど、もとよりそう容易に出来るものではない。しかし、その不可能と思える処に向かって、全精魂と誠の限りを傾け尽くして、我が身をなげうって脇目も振らずに突き進んで行くのである。
多くの修行者達がここで挫折してしまうのは、早急に成果を求めるが故に、三昧境に入ることの困難を痛感してしまうからである。この場合、最も重要なことは、成果を求めず、その時の自己の心境を顧みること無しに、ひたすら「無、無、無」と成り切って行くことである。昔から「鈍工夫」8の必要性が説かれてきたのは、このことである。
そうして月日の経つのも忘れ果てて工夫三昧に没頭していると、これまで有ると思っていた自我が思わず知らず空じられて来る。心を一点に集中していると、公案三昧の恩力によって外界に対して反応しなくなってしまうのは、当然の成り行きである。
歩いていても行き先を通り過ぎてしまい、坐禅していても坐禅しているという意識がなくなる。そうして古人が「寝食を忘ず」と言われた「大死一番」の境涯が現前して来る。しかし、それはそうしようと思って出来るものではない。
三昧境の現前と開悟
この点に関して、鈴木大拙居士が最初に親炙(しんしゃ)された洪川老師の次の言葉が参考になるであろう。「或る人が尋ねた、古人が禅に参じて修行された有様は、工夫純一で寝食を忘ずるほどになったということです。老師の弟子のこの私も、何とかしてその心境に到りたいと思っているのですが、どうしてもできません。そこで私(洪川老師)が答えて言った、それはあなたが大道に切実でないからだ。古人が寝食を忘ずと言われたのは、そうしようと意識してなったわけではない。もし修行者が、ただひとつの切実な問題に心血を注いでいるならば、覚えず知らず寝食を忘じて廃することになる。そうなれば、寝食を忘ずることを止めようと思ってもできるものではない」
(或るひと問う、古人の参禅学道は工夫純一、寝食を忘ずるに到る。弟子、その境界に到らんと欲すると雖も能わず。予が曰く、汝が大道に親切ならざるが故なり。古人の寝を廃し餐(さん)を忘ずは、これ勉強して然るに非ず。もし学人、一の急切事の心に関わる有らば、知らず覚えず寝を廃し餐を忘ず。けだし罷(や)めんと欲すれども能わざるのみ)
このように、「寝食を忘じよう」或いは「見性しよう」ということすら、邪(よこしま)な分別であり、妄想である。この場合、そうしたことを一切考えずに、馬鹿になってひたすら単純な公案そのものに成り切ることが肝要なのである。
それは誠に摩訶不思議な状態である。長い間殆んど寝ていなくても、何ら疲れを感じることがないばかりか、全身に気が充実して八面玲瓏(れいろう)になり、自分の周りの事象も全て透徹して来るのである。外から見れば、疲労困憊(こんぱい)して憔悴しているように見えもするであろうが、当の本人は充実と法悦の極みである。
そして時を忘れて心を一点に集中してすべてを空じ尽くしているうちに、時節因縁が純熟して、何かの機縁に触れて「無の自己」が徹見できるのである。これを「見性」(自性徹見)という。
そうした開悟の機縁はさまざまである。中国唐代の霊雲禅師は桃花を見て悟ったと言われる。そのことを道元禅師9は、「春風にほころびにけり桃の花、枝葉に残る疑いもなし」と歌われた。桃花を見るという機縁によって、迷悟などの分別心も根こそぎになってしまったのである。
公案禅の問題点
ただ残念ながら、現在の公案禅では、透過すべき公案の数が多過ぎるため、師家が初関を比較的早く許してしまう傾向が見られるようである。中国宋代の名僧、無門慧開禅師や無学祖元禅師ですら、初関の透過に六年も要されたというのに、これは一体どうしたわけであろうか。それは本来公案が自己の本心を明らかにする手段であるにもかかわらず、それを透過して公案の数を早く数えることが重要と見なされているからであろう。
しかし、それでは肝心のことが疎(おろそ)かになってしまうのではないか。その上、このような仕方で公案を透過したところで、心からの法悦の醍醐味が味わえるはずもなく、その結果、禅修行も充実感や面白味がなくなり、脇道にそれてしまうことになりかねまい。
自我を破産して無我の端的を体認すること無しに公案の数だけを数えていくことによってもたらされるのは、自我の増長に他ならない。こういう対処の仕方で修行者達を指導しようとする師家は、結局弟子に対して本当の親切心がないという意味で、菩提心の欠如を指摘されても止むを得ないであろう。
日本の禅界では、既に黄檗宗の潮音道海禅師(寛永五年ー元禄八年、1628 – 1695)が当時の状況に関して、この慨嘆を次の如く吐露しておられる(「霧海の南針」:『禅門法語集』至言社 下巻所収)。
「二百年この方、日本では祖師方の公案に著語などしたものを集めて、これらの則を数え終わることを破参大悟と称して、これを箱などに収め、一大事因縁として後生大事にしているが、火事などに出くわせば、そんな一大事因縁は直ちに灰と成ってしまう。
この数え参を教える長老の中には、多聞博学の人はいるものの、名利高慢の心に妨げられて、こうした行き方が誤りであると看破するほどの人も無い。その有様はちょうど鳶(とび)や烏が死んだ鼠を取って秘蔵している様なものである。
これは私が悪口で言っているのでは毛頭ない。仏経祖録の中に先徳の戒められるところである。著語などの意味をも一向に了解出来ずに、仮初めに師家にこれはこうと教えられて言い当てておくだけである。子供がなぞなぞを説く様に覚えるので、自己の本心ははっきりしないままで、公案の数え参が終わった長老の言動も俗人に何ら変わることはない。その上、法慢の為に諸宗を侮り、正法を誹謗する。この故に、二百年以来、禅の燈(ひ)は消えて、正眼の人は一箇半箇もない。
(中略)今どきの数え参を教える智識や長老も、こういう公案の数え参がいつの頃に誰がやり出したかということすら知らず、これを済ますこと無しには修行が済んで出世して長老になることが難しいとばかり思って、そんな修行が一体何の意義があるのかということすら知らない有様である。
私は若年の頃、こうした外道の教えに出会ったが、後になって真正の老師にお逢いして、その非を知ったのである。この様に申すのは、後進の修行者達が同じ様な惑乱を蒙ることを危惧してのことである。道場の看板を掲げて大勢の修行者達を集め、こういう公案の数を数えることを教えて光陰を空しく費やせている人を、果たして智識(立派な老師)と呼ぶべきか、それとも外道と呼ぶべきか」
原点回帰の必要性
潮音道海禅師はこのように喝破されているが、これはご自身も言われているように悪口などではなく、大法の衰退を嘆く禅師の切なる大悲心の現れであろう。いずれの道でも現今はそうであろうが、仏法・禅道・公案禅も、真生命の伝承はまさに風前のともしびである。公案禅をこの窮地から救うと共に、我々自身も真の法悦を得るためには、やはり原点に戻るべきであろう。原点とは「根本の一心を明らかにする」ということである。
それに関しては、抜隊得勝(ばっすいとくしょう)禅師10の言われたように、「即今、見るもの聞くもの、これ何ものぞ」という、見聞覚知する自己の本心を徹見する方法が最善の道であり、公案を見ていくのはその後の方が良いであろう。
この行き方は、臨済宗中興の祖である白隠慧鶴禅師の法嗣(はっす)で高弟の東嶺円慈禅師11も、その「入道要訣」12の中で述べられている。これは、仏道に入るための道筋を五段階に述べられたもので、実参実究する人々にとって、極めて有意義であると思い、現代語訳しておいたので、ぜひ参照して頂きたい。
このリンク先のページから「東嶺和尚法語・入道要訣(現代語拙訳PDF)」がダウンロードできる。
白隠門下の修行者
白隠禅師によって集大成された公案禅の目指す所は、単なる伝統的見解との一致ではなく、自我を尽くして無我の根本的真実を徹見することにあることは、疑いないところである。白隠門下の修行者がこのために如何に血の滲むような骨折りをしたかという実例を、ご紹介してみよう。次の言葉は、霊源慧桃禅師(享保六年ー天明五年、1721 – 1785)が門下の修行者達に回顧されたものである。
「私は昔駿河松蔭寺の白隠禅師の下で修行中、元文五年(1740)の正月より、三種病13の公案に参じ、四年目の秋に、初めてこの難透の公案を透過することが出来た。
その四年の間、人と無用の一言を交えず、可笑しいことも面白いことも無いので、遂に笑うことは無かった。他人が笑っているのを見ると、合点がいかなかった。日暮れになってからは涙を流すのみで、夏も冬も断食し、またはったい粉などをなめ、水を飲んで、七日、五日ずつ、人に隠れて、山中の宮や拝殿などで摂心を行なった。
この歳の冬になって難透の白雲未在14の公案を白隠禅師より与えられたが、疑いは晴れず、十二月初めから庵の戸口に錠を下ろして、隣の家に三日に一度、食事を届けてくれる様に頼んで空腹を癒し、明年二月末まで庵から出ることは無かった。原宿の松蔭寺へは歳暮の礼にも正月の礼にも行かなかった。
そうして二月の末に未在の公案を透過した時の大歓喜は、それこそ筆舌に尽くし難いものであった。三月の初めに年頭の礼に松蔭寺へ参ったところ、禅師は大層悦んで下さったのである」
(『霊源一滴』法語雑集)
霊源禅師はまた別の手紙では、白隠禅師と厳しい先輩の無理無体の責めに会い、五、六度も首をくくろうか身投げしようかと苦しんだ、と述べておられる。公案工夫というものが身命を賭して如何に真剣に行なわれるかが分かるであろう。
富士山の見える松蔭寺では、白隠禅師と遂翁禅師のお墓の周囲を、修行中に不幸にも遷化(せんげ)した修行者達の実に六十四基もの墓石群が取り囲んでいる。彼らは如何に命懸けで修行したことであろうか。禅や公案に対して容易の観をなすことは、厳に慎まねばならない。
最後に、臨済宗の禅僧が、発心して出家し、道場に入門して刻苦し、遂に大悟の春を迎えるまでの有様を、今北洪川老師の修行ぶりから汲み取って頂きたい。
このリンク先のページから「今北洪川老師の禅修行(PDF)」がダウンロードできる。
・次の章「徳川家康の仁政(一)」へ..
・このページのトップに戻る..
- 長養:修行が済み、ある境地を得たといっても、それを真に無碍自在に活用できるようになるがために、容易に世に出ずにさらに心境を錬ること。禅門ではこれを「聖胎(しょうたい)長養」といって尊ぶ。 [↩]
- 見性:自己の本性を徹見すること、悟りをいう。 [↩]
- 摩訶迦葉尊者:釈迦十大弟子の一人で、厳しい修行である頭陀行(ずだぎょう)をもって知られた。禅門では摩訶迦葉は霊鷲山(りょうじゅせん)で釈尊から嗣法されたとされる。 [↩]
- 直截:そのものずばりで回りくどくないこと。 [↩]
- 無門慧開(むもんえかい)禅師(1183 – 1260):中国南宋末の禅僧。我が国の法燈国師心地覚心はその法を嗣ぎ、『無門関』を伝えた。 [↩]
- 無門関:無門慧開禅師が編纂した四十八則の公案集。 [↩]
- 無字(むじ):『無門関』の冒頭に載せられ、古来参禅修行者に最初に課せられる「初関」の典型的公案である。 [↩]
- 鈍工夫:師家から言われた通りに、馬鹿になり切って単純な工夫に全身全霊で没頭すること。 [↩]
- 道元禅師(正治二年〜建長五年、1200 – 1253):道元希玄。日本曹洞宗高祖。入宋して天童山如浄禅師に嗣法し、帰朝して興聖寺や永平寺を拠点に大法を挙揚(こよう)する。その著『正法眼蔵』は日本思想史上屈指の禅体験に関する卓越した表現とされる。 [↩]
- 抜隊得勝禅師(嘉暦二年〜至徳四年、1327 – 1387):臨済宗塩山向嶽寺開山。歴参の後、出雲雲樹寺の孤峰覚明の法を嗣いだ。その仮名法語は有名である。(抜隊仮名法語も非常に優れたものであるので、いずれ現代語訳する予定である。) [↩]
- 東嶺円慈禅師(享保六年〜寛政四年、1721 – 1792):九歳で出家し、古月、翠巌、大道などに歴参の後、白隠に参じてその法を嗣いだ。著作に、『達磨多羅禅経疏』『宗門無尽燈論』『五家参詳要路門』『快馬鞭』などがある。 [↩]
- 入道要訣:『快馬鞭』の上巻を成す。 [↩]
- 三種病:乾峰と雲門という二人の中国の名僧に関わる、「法身(悟りの当体)に三種の病と二種の光がある」という難透の公案である。 [↩]
- 白雲未在:中国宋代の白雲守端がその法を嗣いだ五祖法演に示した公案で、五祖はこの公案によって真に徹底することができた。 [↩]