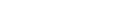「三昧境への道」2025年04月【No.260】
最近、長年無字の公案三昧の工夫を続けている男性から、「自分なりに工夫に励んでいるのですが、無―の充実、三昧境までなかなか到りません。毎日の生活において、日々なすべきことをもう一度ご教授頂けませんか。何でもやります。毎日やります。必要であればお寺にも伺います。どうぞよろしくお願い申し上げます」という切実な問い合わせがありました。私は「無―と絶えずやっていくと、いつのまにか三昧境に入って行くものです。あせらずにやっていくことです」と返信致しました。工夫する人の多くはどうしても成果を求めてあせりがちになるようです。私は修行中にあせりを感じたことはありませんでした。あせりを感じるというのは雑念を起こしているということに他なりません。あせりなど感じることがないほど工夫に没頭すればよいのです。
在家の人が日常生活を送りながら工夫三昧になるのは至難のわざですが、不可能なことではありません。私が尊敬している片岡仁志先生(京都大学教育学部名誉教授)は20歳の時に肺結核にかかりながら、病院のベッドの上で坐禅三昧に打ち込んで、ついに見性(お悟り)の眼(まなこ)を開かれました。
もとより三昧境は目指す到達点ではなく、途中の風光にほかなりませんが、三昧境を経験していない人が解脱(お悟り)を得るということは不可能です。しかしほとんどの人がなかなか三昧境に到達することができないのは、四六時中真剣に工夫することをやっていないからだと思います。私自身の体験から申し上げれば、真剣に工夫すれば三昧境に入ることはさほど難しいことではありません。ただ成果を求めず、ひたすら目の色を変えて工夫三昧に打ち込んでいれば、期せずして三昧境が現前するものです。これを「鈍工夫」と申します。分別を起こさずに馬鹿になって工夫に没頭するだけです。
ただ専門道場で修行する雲水でも、この三昧境の法悦を味わうことのできた人は稀のように思います。白隠禅師が言われているように、数息観によって計り知れない三昧境に入ることが可能ですし、また無字の公案工夫を真剣にすれば無字三昧の法悦を味わうことができます。皆さん方も真剣に工夫してこの法悦の醍醐味を体験されませんか?