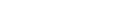「名僧の修行ぶり(通翁鏡圓禅師)」2023年05月【No.238】
私は令和2年末以来、南禅寺本山の機関誌である「瑞龍」(南禅寺の山号を瑞龍山と称する)誌上に「古佛の芳躅(ほうちょく)」と題して名僧方の修行経歴を連載しております。
「古佛」とは特にずばぬけた名僧を尊称していう呼び名であり、「芳躅」とは古人の示されたすぐれた行跡を意味しております。出家して一生をなげうって佛道を究めるために修行しようという若者がほとんどいなくなって、宗門はまさに危機に瀕しているといっても過言ではありません。この危難を挽回するための一助となればと思い、「古佛の芳躅(ほうちょく)」と題して、格外の名僧の行履(あんり)をご紹介しております。ただこれは本山の機関誌に掲載されるだけですから、禅の修行に関心のある、より多くの方々にもごらん頂きたいと思い、このたびこのコラムにおいてもご紹介させて頂きたく思います。
第一回目に採り上げたのは、南禅寺第八世の通翁鏡圓禅師(普照大光国師)(1258―1325)です。国師は後の大徳寺開山・宗峰妙超禅師(大燈国師)を侍者として臨まれた南都北嶺の学匠との「正中の宗論」に、病を押して参加され、その帰り道に遷化(せんげ、亡くなる)されましたが、その際の後醍醐天皇ご下賜(かし)の籠が、南禅寺の国宝・清涼殿の一角に展示されております。
この通翁鏡圓禅師は本当に古人にも稀なる骨折りをされた方です。那須の雲巖寺の高峰顕日(佛國禅師)に参じ、また筑前横嶽(よこたけ)の崇福寺の南浦紹明(大應国師)に参じて、那須に到ること十七回、横嶽に上ること十七回に及んだといわれます。禅門では、雪峰義存禅師の「三到九至」(三たび投子大同禅師に参じ、九たび洞山良价禅師に参じた)の行脚歴参が有名ですが、通翁鏡圓禅師がその当時の二大甘露門(名僧)に参じられた行履も、それに勝るとも劣らぬものでしょう。これは名利の念や、修行をなるだけ早く済ませて住職となりたいなどという思いが微塵でもあれば、到底出来ないことです。ただひたすら佛道を究めんとする必死の願心あるのみであったことでしょう。
那須から筑前までは徒歩で一体どのくらい日数がかかるのか想像もつきませんが、後年白隠禅師がそうされたように、行脚しながら禅師はひたすら公案三昧に没頭されたに相違ありません。私自身にもささやかな経験がありますが、歩きながらの公案工夫は非常にはかどるものです。禅師がこの長距離の風餐(ふうさん)露宿(雨にさらされて食事をとり、露に濡れて食事をとること)行脚を十七たびも敢行された刻苦は、われわれには到底及びもつかないことですが、こうした禅師の気高い求道心を仰ぎ見て、私たちもいささかでも分に応じて修行に励もうという菩提心を高めて行きたいものです。
さて、禅師の開悟の因縁は、南浦紹明禅師の会下(えか)として修行中、或る時、一人の僧が屋上の松を指して、「一切の草木、皆山河大地を以て縁となす。渠(かれ)独り何を以て縁となす」と問うと、他の僧が「無縁を以て縁となす」と答えました。この問答を傍らで聞いていた禅師は豁然として大悟し、直ちに南浦禅師の丈室に趨(はし)って悟った境地を呈したところ、南浦禅師はすぐさま印可(お悟りの証明)を与えたと伝えらます。
このことから看て取れるのは、南浦禅師の室内では、公案の調べを済ませて初めて印可証明を授けるのではなく、真に徹底して悟りを開けば、それで
印可を授けたということです。「直指人心、見性成佛」を標榜する禅宗では、何よりも見性の根本経験が不可欠です。中国で臨済宗中興の祖と尊称される五祖法演禅師が霊源惟清禅師に宛てた尺牘(書簡)には、「諸荘の旱損(かんそん、日照りによる損失)、我総に憂えず、ただ禅家に眼(まなこ)無きことを憂う。今夏百余人室中に箇の狗子無仏性の話(無字の公案)を挙するに、一人の解得(げとく、悟る)する無し。此(これ)を憂いと為すべし」(『禅門宝訓』)とあります。
一人でもこの通翁鏡圓禅師の尊い芳躅に触発されて、命がけの工夫三昧の法悦を体現する雲衲や在家の人が出現して頂きたいものだと願わずにはおれません。