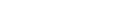「夏日の法悦」(月刊コラム【No.110】2012年8月)
連日の猛暑が続いている。こんな炎天下でも外で働らかざるを得ない人々はさぞかし大変であろうと拝察する。まことにご苦労様である。この光雲寺では「南禅寺禅センター」として毎月大勢の坐禅を実施しており、例年なら暑い七,八月は極端に坐禅希望者が減るのであるが、今年は京阪バスの定期観光バスでゆく「バスガイド企画コース」という、バスガイドさんたち自身が作った「心で観る京都」の企画の一環として、光雲寺での坐禅体験を希望する人たちが毎週の半分くらい来訪する。おそらくこれまでの特別拝観中にお客さんたちを連れてこられたガイドさんたちが、光雲寺の風情に何かを感じてこの企画を立ててくれたものと思われる。
観光ツアーなので物見遊山半分かと思われるかも知れないが、酷暑にもめげずに皆さんが非常に熱心に坐禅しておられるのには感心する。坐禅を始める前の説明で「本当に工夫が乗ってきたなら、抽解(休憩のこと)で足を解くのも勿体ないという気持ちになるはずである」というと、十五人の参加者のうち、誰一人として足を解く人がなかったのには、こちらの方が驚いて感心したほどである。中には本式の結跏趺坐したまま微動だにせずに坐っている人もおられる。坐禅のあともお抹茶を飲んでゆっくりされるので、こちらも普段はお見せしない寺宝の数々をご覧頂き、皆さん方も驚嘆と笑顔で下山されていくのを見るのは、暑さも忘れてしまうような心地よい気持ちになるものである。
江戸時代後期の天保十四年(1843)に刊行された『雲萍(うんぴょう)雑志』という随筆がある。平明な文章で書かれ興趣に富んだ例話が豊富で、江戸時代の随筆の白眉であるという人もいる。岩波文庫で版を重ねているが、著者の柳澤淇園説には、校訂者で伝記学の大家の森銑三氏が疑問を呈しておられる。ともあれこの随筆は小衲の愛読書の一つであるが、その中に一読して忘れ去ることのできぬ印象をもった「夏日の七快」という一段がある(岩波文庫本、七十六頁)。
「○夏日の七快
湯あみして髪を梳(くしけず)る。掃除して打つ水したる。枕の紙を新たにしたる。雨晴れて月の出でたる。水をへだてて灯(ともしび)のうつる。浅き流れに魚の浮かみたる。月の差し入りたる。」
江戸時代の人々は炎熱の時節にもとより冷房とてあるはずもなかったが、現代人よりもよほど日々の暮らしの中でささやかな楽しみを見いだすことに長(た)けていたように思われる。わが国を訪れた外国人たちの豊富な証言に基づいて構成された渡辺京二氏の大著『逝きし世の面影』を読むと、江戸時代の人々がいかに人生を謳歌していたかがよく分かる。
さて、『雲萍雑志』の「夏日の七快」に対して、この光雲寺の「夏日の七快」を挙げるとすれば、どうなるであろうか。「1, 早朝に誰よりも早く起きて抜かりはないかと念を入れながら粥座(朝食)の準備をする。2,柴犬を連れて散歩をすること。3,池の鯉にえさを撒くと浮き上がって夢中になって食べる様。4,苔庭に朝夕に水を撒くと日中の照りつけで赤茶けていた杉苔が青々してくること。5,庭師さんが定期的に来て綿密に庭の手入れをしてくれた庭が、毎日草引きをしたあとでますます綺麗になって行くのを実感すること。6,坐禅や人生相談に来られた人たちが喜びに満ちた顔で帰られる時。7,たとい多忙を極めていてもゆとりと喜びをもって物事に対処できた時。」
思いつくままに挙げるとすれば、そのようなところであろうか。しかし禅にはまた一段と格別の「法悦」がある。「無字」なら「無字」の公案を四六時中目の色を変えて「むー、むー」と拈提していけば、いつの間にやら三昧境に没入して自己が空じられ八面玲瓏となる。この工夫は中途で止めては駄目で、決死の覚悟でぶち抜くまで貫徹しなければならぬ。
小衲の知り合いで一旦道場を離れて日雇いの在家生活をしている者がいる。彼は炎天下の肉体労働の只中で、初めて小衲が常日頃力説していた「四六時中の公案工夫」の絶大なる成果に気づいたもののようである。「むー、むーとやっていると、暑さを忘れ、時間も忘れ果てて、ふっと気がつけば長時間が経っていました」と述懐したので、小衲は思わず呵々大笑して、「禅の道場を離れて却って禅に触れることになったな」と彼に言った次第である。ただこれはほんの「さわり」といってよい。それを真実の法悦体験を得るまで飽くことなく突き進むことができるかどうか、は本人の道心次第である。世俗的なことに心を動かされるようなことではとても成就できるものではない。ともあれこの悦びに勝る「夏日の法悦」はあるまい。禅に接した人たちがもしそこまで徹底しようとしないならば、それは本当に勿体ないことではないであろうか。