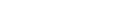「宮本常一の業績」2013年2月【No.116】
皆さんは宮本常一(つねいち、明治40年ー昭和56年、1907—1981)の名前をご存知だろうか。山口県の周防大島出身の民俗学者である。その著作『忘れられた日本人』が岩波文庫百選に入っているので、読まれた方も多いであろう。殊に佐野眞一氏の『旅する巨人』という好著が16年前に刊行されてから、宮本常一の業績に関する書物は増加の一途を辿っている。
佐野眞一氏といえば、最近は橋下大阪市長の出自を週刊誌上に差別的表現で書き表したとして諸方から顰蹙をかったノンフィクション作家であるが、この『旅する巨人』はなかなかどうして、宮本常一とその生涯を支え続けた渋沢敬三とに関する並々ならぬ熱意と思い入れによって貫かれた力作である。小衲はこの単行本が出るやいなやすぐさま購入したが、それは、「これはぜひとも読んでおくべき書物である」と直感したからに他ならない。こういう好著を書くことのできる人物がなぜあのような晩節を汚すような一文をものしたのか合点がいかないのである。
佐野氏のことはともかくとして、最近また宮本常一の著作や関連書籍を読む機会があり、ますますその後世に残した足跡の比類なき偉大さに瞠目せざるを得ない。民俗学者としては柳田国男の名がつとに知られている。明治6年に兵庫県の儒者の家に生まれ、苦学して東京帝大法科を出て高級官僚になった柳田は、講演旅行などで地方の実情や民俗に触れて大いに興味をもち、全国各地を調査して日本民俗学を確立するに至る。著作としては名著『遠野物語』がもっとも人口に膾炙しているであろう。
数年前に柳田国男の生家を偶然見つけて訪問したことがあるが、そこには「日本一小さな家」とかいう表示が掲げてあった。しかし「日本人とは何か」という課題を解くべく各地を調査した柳田は、所詮庶民目線の人ではなかったように思われる。正三位勲一等を叙勲した柳田は、民俗学の調査に際してはいつも最高級の旅館に宿泊したという。しかも柳田は病弱の人に対していたわりの情に欠けるところがあったという証言がある。宮本が次第に柳田とは疎遠になって行ったのは無理からぬことのように思われる。
これにたいして宮本常一は一日あたり40キロを踏破し、73年の生涯に合計16万キロ、ちょうど地球を4周するほどの行程をひたすらわが足で歩き続け、泊めてもらった家は千軒にのぼるという。しかも余人の滅多に行かぬ辺鄙な山奥にまで分け入っている場合が普通である。彼は自ら農民として郷里で農業を営みながら、農業の民、海の民、山の民といった常民の目線で、戦前・戦中・戦後のあるがままの日本人を記録していった。抜群の人柄で聞き上手であった彼は、余人の追随を許さぬほどの厖大な聞き取りをし、生前の昭和41年(1976)から刊行が開始された『宮本常一著作集』(未來社)は現在のところ51巻が刊行されているが、全著作を網羅すれば100巻は優に越えるといわれている。
しかも宮本常一の業績はこのような民俗学的著述だけに限定されるものではない。離島振興のために尽力し、そのための法律の制定にも奔走した辺境の指導者であり、各地の卓越した農業・林業・漁業の技術を足実地を踏んで調べ上げ、それを全国に伝え指導して歩いた経世済民の人であり、地域に残された芸能などの発掘と育成を通じて地域を活性化させた人である。
宮本常一の超人的努力により、われわれは高度成長期以降の日本からはほとんどその姿を消してしまった「本来の日本人」の何たるかを知ることができる。民衆はブルジョアにより抑圧された哀れな生活を送ってきたという左翼的思想が戦後になって一世を風靡したが、足実地を踏んで全国をくまなく精査してきた宮本常一は、このような観念的・イデオロギー的解釈に決して組することはなかった。
宮本常一の著作を読むと、古来から日本の底辺を支えてきた農・山・漁の民衆たちが精一杯働き、工夫して、ささやかながら日々の生活を享受してきた経緯がよく分かる。それにしても心が痛むのは、一日中、身を粉にして働いたとしても、流通などの不十分な時代には、郷里だけでは到底食べていくことができずに、身売りや出稼ぎなどが当たり前であったという事実である。
小衲自身は都会生まれの都会育ちで、農・山・漁で生計を立ててきた人たちの知り合いがほとんどないに等しい。自坊の檀家さんたちもまたそうした職種の人は皆無といってよい。しかし日本という国がいかにして成り立ってきたか、どういう人たちが支えてきたかという点に関しては、知っておくべきであると思うのである。歴史的文献に残っているのはほとんど支配層に関するものであり、またそうした立場からの記述である。宮本常一の業績の重要性はこれからますます自覚されて来ることであろう。
最後に言及しておきたいのは、宮本常一が恩師の如くに敬愛し、恩義を感じて、毎夜枕元にその写真を飾ったという渋沢敬三のことである。言うまでもないことであるが、渋沢敬三の祖父は「日本資本主義の父」と称された渋沢栄一である。東京帝大を出て日本銀行総裁となり大蔵大臣まで上り詰めた渋沢敬三ではあるが、それよりも自らも大民俗学者として宮本常一のかけがえのなさを知り尽くして、物心両面から宮本を支えた偉大な人物である。
この渋沢敬三が宮本常一に助言した言葉が宮本の自伝とも言うべき『民俗学の旅』の中で述べられている。「大事なことは主流にならぬことだ.傍流でよく状況を見ていくことだ。舞台で主役をつとめていると、多くのものを見落としてしまう。その見落とされたものの中に大事なものがある。それを見つけていくことだ。」まさに珠玉の言葉といってよい。宮本常一はもし渋沢敬三との出会いがなかったならば、これほどの成果を上げることができなかったであろう。それを一番知っていたのは他ならぬ宮本自身である。
宮本常一がいかに素晴らしい業績をあげた人物であったかは、彼に親炙した著名人で彼に傾倒する人が枚挙に暇がないことでもよく分かる。例えば、水上勉は『飢餓海峡』という小説を書いた際には現地に行くことなく五万分の一の地図を見て書いたという。その結果、電気の引かれていないところで裸電球が使われていたというような出鱈目を書いたが、小説だからそれで通るが、「宮本先生のお仕事を見ていると恥ずかしい気持ちがいつもして・・・・」などと率直に述懐している。
また司馬遼太郎も宮本のことを「先生」と呼んで畏敬し、宮本が亡くなった時には郷里の周防大島まで弔問に出向いたという。司馬遼太郎は自作の「花神」に関するエッセーで、「大村益次郎が豆腐好きだということは歴史好きの人なら知っている。その益次郎がどういう食器と箸で薬味は何で豆腐を食べたかまでを調べたのが宮本常一氏なのだ。本当に宮本さんという人は恐ろしい人だ」と述べている。
さらに面白い話がある。日本霊長類学の創始者で京都大学名誉教授の今西錦司の文化勲章受章記念パーテイーがあった時のことである。弟子の梅棹忠夫などが列席していたが、今西錦司は苦虫をかみつぶしたような顔をしていたという。ところがひとたび宮本常一が会場に姿を見せると喜色満面となって応対したという。今西にとって直弟子よりも評価し心の許せる人物が宮本常一であったということの証左になるであろう。
天王寺師範出身の宮本常一は東大や京大から招聘を受けたが、渋沢敬三が宮本のことを思ってこれを断り、武蔵野美大の教授となった。有名国立大学教授とならなかったのはいかにも宮本にとってふさわしい。テレビなどの普及で、戦後ますますわが国は全国的に画一化された結果、文明に汚染されていない地域はほとんど地を払って消失したので、時代的にももう彼のような人物の出現は望めないであろう。
ともあれ宮本常一は、宗教や禅に関心があろうとなかろうと、知っていなくてはならぬ重要人物のように思われるのである。