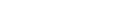「家康公と秀忠公」(月刊コラム【No.101】2011年11月)
NHKの大河ドラマの主人公である「お江」は、先月のコラムで申し上げた通り、この光雲寺を菩提寺として再興された中興開基である東福門院(源和子)の母君であるという因縁で、毎回どのように演じられているのかを興味を持って拝見している。しかしどうも史実とはかなり異なる場面が随処に見受けられるのは残念な気がする。
そのように作りごとを織り交ぜて視聴者を飽きさせないようなドラマを作るというのが原作者やディレクターの意図らしいが、あまりにも極端な虚構が多すぎては、視聴者にかえって敬遠されてしまうのではないか。特に信長・秀吉・家康に関しては詳しく知っている人たちが多いのであるから、色々と酷評されるのは織り込み済みのことかも知れない。しかし本来は史実を基本として、虚構はあたう限り最小限に止めるべきではないだろうか。
小衲が特に気になったのは、家康公と秀忠公とのやりとりである。秀忠公は大御所である父・家康公のことを「おやじ」などと現在の若者言葉で表現しているが、これは決してあり得ないことである。また秀忠公は「おやじ」に反抗するばかりの息子として描かれているが、これはまったく史実に反することである。おそらく百戦錬磨の家康公の存在は秀忠公にとって容易に反抗しかねるほどの威圧感があったに相違ない。
大坂出陣の際に、いち早く京都にのぼった家康公に対して将軍秀忠公が思いのほかに到着が遅れたので、家康公は大いに立腹された。これを聞いた秀忠公があわてて三河よりわずか三十騎の手勢で急ぎ駆けつけると、家康公は顔色を変えて立腹し、「将軍となり、わが子として生まれてきて、そのように武家(弓矢)の道に疎いようなことでは、どうして天下の守となられることなどできようか。『将軍が遅すぎる』とわしが立腹するのを聞かれれば、『それは家康公がもうろくされていわれているに相違あるまい。大坂の者どもが京都に攻め上るなどということは想像もできない。万事はまた軍兵が疲労しては軍が立ちゆかぬ。急ぐまでもないことだ』と、ゆっくりと来られてこそ将軍の分別にふさわしいというものである。わしが立腹しているからと聞いて、一騎にて急ぎくるような分別では、天下の守となられることなどできようか」といよいよ立腹されたということである。これは「家康公逸話集」である『披沙揀金』(369頁)に見られる逸話であるが、もののふの道に関しては親子の間で格段の円熟度の違いがあるのが見てとれるであろう。
また家康公は重臣を介して将軍秀忠公に対して、「古人の申すことは益が多い。夜長なときには藤堂(高虎)などを召し寄せて御夜話をさせられたらどうか」と進言され、将軍はそれを快諾して実行し、得るところ多大であったという。或るとき家康公は「武士は武勇が第一であるが、そうはいっても武は過ぎては臆病よりも劣ることになる。武田勝頼は長篠合戦の際につねづね武勇に過ぎた振る舞いがあったのを、こちらがよく見透かし、ゆとりを持って対処したところ、あの通りの辛抱げのない気性ゆえ、むちゃな戦を仕掛けてたちまち滅んでしまった。もしひたすら臆病であれば、家老の熟練者の意見を採用してなかなかもろくは滅びることはなかったであろう。天下を知る身にとっては慈悲ほどよいものはない。しかし慈悲も度を越してはむごきにも劣ることになる。武家の作法を忘れ、弓馬のたしなみがなく、人馬ももたず・・・ほしいままに身をもつ者をそのままに放置すれば、それを見習って習わしが悪化することになる。そのような時には、見せしめのために2,3人もむごく処置すれば旗本中の眠りが覚め、習わしもよくなり武家長久の基となると思う。和泉(和泉守、藤堂高虎)よ、どう思うか」と尋ねられたので、高虎は「いかにもいかにも御意の通りでございます」と申し上げたところ、家康公は「そうならば将軍の夜咄(よばなし)にそのことを申し上げよ」といわれた。
夜咄の折りに高虎がその通りに申し上げたところ、将軍は大いに感心され、「武勇と慈悲とは第一の善事である。その善いことも度が過ぎればよくないとの御意である。後々まで語り伝えて子孫の手本とするように」と自筆でお書きになった。その翌日、高虎がことの次第を申し上げると家康公は、「将軍は立派な大将であるからこのようなわきまえがないわけではなかろうが、孝行心が深いがために自筆で書き留めて子孫にも伝えるべきであるという心がけである」と、家康公は深く感じいられた様子であったという(同上書、551頁)。
また『松永道斎聞書き』という家康公の逸話聞き書きには次の話が載っている。
家康公が駿府城(静岡)におられた時、江戸で将軍秀忠公が太田という武士に知行五百石を下されたのであるが、その知行の折り紙の詞令書を、太田は秀忠公の御前に投げ捨てて退出した。そのため秀忠公はことのほかお怒りになり、この者を罪に処すことを申し渡すというお気持ちであった。ところが、井上主計頭(かずえのかみ)正就(まさなり)がそれを伝え聞いて、「この太田と申す者は家康公と親密な間柄の者でございます故、なにとぞ一度家康公の方にこの件につきましてお尋ねされた方がよろしかろうと存じます」と秀忠公に申し上げた。「それならばお前が駿府に参上して、この経緯を申し上げよ」という秀忠公のご意向により、主計頭が駿府に参上することになった。それは、秀忠公はすべてどのような事でも、「駿府様(家康公)のお名前を申し上げれば、憤激するのをやめられるので、主計頭がそのように申し上げた次第である。
主計頭が駿府へ参上し、家康公にお目見え申し上げたところ、家康公が「江戸は変った事はないか」と尋ねられた際に、主計頭は「江戸は別に変った事などございませぬ。このたび私をお城に遣わされましたのは、先日太田某に対して秀忠公が知行五百石を下されましたところ云々」と経緯を謹んで申し上げた。家康公はことのほかご機嫌のご様子で、「さてさて、松平(徳川家)が栄えるのは目出度いことだ。その不敬無礼ということは、かの太田が言うべきものではなく、ただ将軍こそ言われるべきものである。その訳は、秀忠公は天下の主(あるじ)である。世は太平で、位は三公(太政大臣・左大臣・右大臣)であるから、どれほどご遠慮なく裁断致され、太田の如き者がこのたびの無礼の十分の一のことをしでかして、どのような罪を科せられようとも、天下の者のうち、一体誰が道に反したことだなどと将軍のことを言うであろうか。それにもかかわらず、将軍が、彼に賜った知行が果して彼の功績にふさわしくないのでありましょうかと、このわしに尋ねんがために、貴公をこの駿府城まで遣わされたということは、まことに将軍が天下の政事(まつりごと)に心配りをされることが並々ならぬ証拠である」、こう言って、家康公は涙を流された。
そして家康公は、主計頭に対して、「このことに関して一つの物語をするので、よくよく承知しておくように」と申し渡されたのである。「わしが三河城におった時、勅使やその他の公(おおやけ)のことがあるであろう時のために、三尺(90センチあまり)以上の大きな鯉を庭の池の中に放しておいたところ、池の中を見ると、とりわけ大きな鯉一匹が見当たらぬ。そこでその場所を担当している掃除坊主に、『囲みが不十分だったので、狐にでも捕られたのか』と言えば、この者が申すには、『その鯉は鈴木久三郎が拝領申し上げたということで御台所へ持参致し、料理して人々にも振る舞い、信長公より頂戴した酒を試し飲みせよとの殿の御意とのことで、酒樽の封を切って頂戴致しました』と言うので、台所係に尋ねればその坊主の申した通りであった。鯉も酒もわしでさえ食べるのを控えておるのに、何という勝手気ままな奴だ。そのような者をそのままにして置くならば、これから諸士の風儀が悪くなるはずだと思い、呼びつけて成敗(斬り捨てに)せねばならぬと決心して、鈴木を呼びにやった。
薙刀(なぎなた)の鞘(さや)をはずし、広い縁側に出て鈴木を待っていると、久三郎は同輩らがひそかに自分のことを密告したにもかかわらず、一向に平気な顔でわしの前に出頭してきた。そこで十間(けん、十八メートル以上)ほど距離を置いて、「にっくき奴め」と言葉をかけ、薙刀で斬り捨てんとしたところ、久三郎はこれを見て自分の大小の刀を五・六間ほどあとに投げ捨て、わしに向かって大きな目を見開いて、「さてさて、何という愚かな御大将(おんたいしょう)であらせられることか。魚や鳥が人に匹敵するという作法など、一体どこにあると言われるのか。そんな有様では、天下統一の願望など到底成就しませんぞ」と、久三郎はかえってわしのことを悪し様(あしざま)に罵った時に、「その通りだ」と思い当たり、抜いていた薙刀を棄てて部屋の奥に入り、よくよく彼の心中を推察するに、近頃召使いの者が、一人は狩猟厳禁の留場(とめば)で鳥を取り、一人は城の堀で網を打って魚を取ったので、この両人を閉じ込めておいたが、そのことを言わんがためにわざと鯉を料理したのであろうから、一向に不敬無礼なことではない、ひとえにわしの処分を悲嘆して行なったことであると思案したのである。
そこでかの両人を奉公に出すようにと言い渡した時、久三郎を呼び出し、「貴公の高邁な気持ちを嬉しく思うぞ」と言うと、久三郎は涙を流し、「何という有難い仰せでございましょうか。太平の世でございますれば、ひそかに申し上げるべきことではございましょうが、今は国が乱れている時節なので、かように申し上げた次第でございます。乱世には私の如き末端の侍も、多少の勇気があるものでございますれば、殿の御為(おんため)と思い、あのようなことを申し上げたのでございます。決して決して利己的な心をもって強がりを言い、自分勝手な気持ちで申し上げた訳ではございませぬ」と言ったので、わしは一層彼の忠信(まごころを尽くし、うそ偽りのないこと)を痛感し、格別のことと思ったのである。
「昔も今も諸士が忠信であるかは大将の心に存している。このようなことを武道に不案内の者が中途半端に聞けば、この者が武功を自慢しているかのように言って懲らしめるものである。心を鎮(しず)めて聞くがよい。忠信の者でなくては、思い切った言葉を言わぬものである。主君というものは恐ろしいものなどないので、主君の気に入らぬ諌言など申すことは、合戦場で大敵の中へ駈け入るよりも一段と厄介なことである。
その訳は、大敵の中へ駈け入った場合には大勝利を得る者が多い。主君に悪く思われては、場合によってはわが身ばかりか妻子の命さえも免れ難いことがある。それを知りながら、そうした歴史上の出来事をも顧みず、思い切って言うのは、勇敢きわまりない者、忠信この上ない者である。総じて国を治める天下の主(ぬし)たる者は、沈みかけた船の中に坐し、燃えている家の下で寝ているような心配りを忘れることなく、諸人の気持ちを推察し、たとえ何の役に立たないことであっても、思い切って言ってくれた言葉をむざむざとは放置しないものである。
以上が『松永道斎聞書き』に見られる家康公と秀忠公との逸話であるが、大河ドラマの人物像とはまるで相違して、さすがは天下統一を成し遂げた器量のある親子関係ではなかろうか。このコラムが大河ドラマの偏見を是正する一助となれば幸いである。
(なお光雲寺では11月21日(月)より12月4日(日)午前9時から午後4時まで特別拝観を行います。どうぞお誘い合わせの上、お越しをお待ち申し上げております。11月27日の月例坐禅会は南禅寺山内の南陽院様を拝借して行います)。