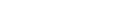「幽谷深山、華自ずから紅なり」2015年11月【No.149】
今年も二人の日本人研究者によるノーベル賞授与が続いたことは、誠に喜ばしいニュースとして日本中を駆け巡りました。生理学・医学賞の北里大学・特別栄誉教授の大村智(さとし)氏と、物理学賞の東京大学教授の梶田隆章(たかあき)氏です。お二人とも山梨大学と埼玉大学という地方大学の出身者です。特に大村氏に関しては、「2億人を病魔から守った科学者」とか「産学連携の先駆けで、それによって得た250億円を北里研究所の発展のために寄進した」というニュースが流れましたので、氏のことをもっと知りたく思い、馬場錬成氏による大村氏の伝記(中央公論新社刊)を取り寄せて拝読しました。
「大村先生の業績を広く知ってもらうため」という願いをもつ元特許庁長官の荒井寿光氏に伝記の執筆を依頼された著者の馬場氏が、大村氏に長時間インタビューしてその生涯と業績とを細部に到るまで克明に調べあげ、力作と呼んでしかるべき実録伝記を完成される原動力になったのは、初めてお目にかかった際に「大村先生の識見とお人柄に触れ」て感激されたからでしょう。テレビで拝見した大村氏には確かに他人を魅了する風格が感じられました。しかし事ここに到るまでにどれほどのご苦労と研鑽があったのかを、伝記を拝読して思い知った気がします。
大村氏の受賞理由はブユが媒介する寄生虫病であり、網膜に入り込んでしまうと失明するに到る熱帯地方のオンコセルカ症(河川盲目症)という感染症の特効薬であるイベルメクチンの開発でした。微生物や細菌が身を守るために産生する化学物質の中には人間や動物に有用なものが少なくありません。しかも大村氏はその開発を米国の大きな製薬会社であるメルク社と共同で行い、その特許で生まれた製品があると、その売り上げ高に応じてメルク社は北里研究所にしかるべき対価を払います。こうして支払われた対価の総額が250億円を越えたということです。単に研究者たるに留まらず、「研究を経営する」という辣腕の経営者としての才覚があったからこそ、経営不振に陥っていた北里研究所を見事に建て直すことができたのでしょう。
馬場氏が伝記を書きたいと申し出たとき、大村氏は「生まれ故郷の土地を見てもらいたい。自然と接して育った少年時代を抜きにして私の研究人生は語れない」と話されたということです。昭和10年(1935)に甲府盆地の豊かな自然の中で育った大村少年は農家の長男として野良仕事を手伝うと共に、父親から家長となるべく厳しい教育を受けました。農作業を手伝うことによって様々な自然現象への興味が身についたということです。大村氏はこの子供時代の経験について、「農作業の計画と実行は、化学における実験や作業計画とよく似ている。どちらも、将来を見越して計画を立て、臨機応変に変更していく。農業とは自然を学ぶことであり、農民は自然科学者であると思う」と言われたということです。足実地を踏んだ人の堅実な言葉ではないでしょうか。
父親は成績が極めて優秀だったのですが、18歳の時に父に死なれ、長男であったので進学を断念しました。大村少年が中学生の時に部屋の片付けをしていて、教科書とノート類からなる30冊以上の「高等講義録」を見つけたのですが、それは父親が多忙な農業の仕事の寸暇を惜しんで通信教育で勉強していたもので、大村少年は感動して、怠けていたわが身を反省したそうです。
また母親も20年間の教師生活をした後、農業や養蚕などに従事しましたが、特に養蚕の手法や結果が克明に書かれた日誌を見せられて、大村少年は非常に感銘を受けました。母親の教師時代の日誌の最後の頁には、「教師たる資格は、自分自身が進歩していることである」と書いてあるのを見つけて、大村少年はこの言葉を肝に銘じて生きるようになったといいます。
こうしてみますと、大村氏の今回のノーベル受賞の一番の土台となったのは、古き良き時代の日本人を彷彿とさせるご両親の生きざまであるとは言えないでしょうか。大分県国東半島出身の孤高の自然哲学者・三浦梅園(享保八年—寛政元年、1723−1789)に「人生恨む莫(なか)れ、人識る無きを。幽谷深山、華自(おの)ずから紅(くれない)なり」(人生莫恨無人識、幽谷深山華自紅)という漢詩があります。「他人が自分のことを知って評価してくれなくても嘆くには及ばない。深山幽谷に咲く花は、誰に見てもらおうという思いもなく、また誰からも顧みられることなくとも、精一杯見事な花を咲かせている」という意味でしょう。甲府盆地のただ中で実直に愛情を込めて子息を育てられ、将来のノーベル賞受賞者になられた下地を作られた大村氏のご両親に、「幽谷深山、華自ずから紅なり」の句を捧げたいと存じます。