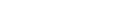「無字の公案」(月刊コラム【No.104】2012年2月)
およそ臨済禅に参ずるものにとって、無門慧開禅師の『無門関』の第一則「趙州無字の公案」(或いは「趙州狗子」や「狗子無仏性」ともいう)はもっとも基礎的な公案である。「趙州和尚、因みに僧問う、狗子に還って仏性有りや也た無や。州云く、無」。
釈尊が大悟の際に「奇なるかな、奇なるかな、一切衆生、尽く如来の智慧徳相を具有す」といい、『涅槃経』の師子吼菩薩品に「悉く仏性有り、如来は常住にして変易有ること無し」とあることからすれば、眼前の犬に仏性がありますかと問われて、「無」と応じた趙州のいう「無」は無門慧開のいうように「有無の無ではない」のは明らかである。
ただ「公案」というものは、それについてとやかく論じたり分別したりすべきものではなく、わが身を擲ってこれに参じて実参実究して分別を蕩尽すべきものである。「無字の公案」は五祖法演や法孫の大慧宗杲あたりから盛んに用いられ、無門慧開が『無門関』の第一則に掲げるに及んで、参禅して師家から授けられる最初の関門(初関)として定着したのであるが、それにとどまらず、「宗門の一関」としてすべての公案の根本である。
五祖法演が霊源惟清に宛てた書簡には、「諸荘の旱損(かんそん)、我総に憂えず、ただ禅家に眼(まなこ)無きことを憂う。今夏百余人室中に箇の狗子無仏性の話を挙するに、一人の解得する無し。此を憂いと為すべし」(『禅門宝訓』)とあるが、いにしえの雲衲もこの「無字の公案」を透過するのに苦心惨憺したと見える。
もとより公案禅の弊害については、中峰明本の師である高峰原妙がすでに、その当時の禅僧たちが、往々に上求菩提・下化衆生という「出家の本志」を忘却して真実の悟りを求めず、古則公案を頭で穿鑿した「調べ」を師から弟子へと伝授し密かに珍蔵して、それこそが「極則」であるかのように主張しているが、肝心の大死一番・絶後再蘇を経て自性を徹見していないので、人我や三毒が益々猛威を振るうと、嘆いている(『高峰大師語録』補遺)通りである。しかし他方、この「無字の公案」の恩力によって見性の眼を開いた禅僧が数多くいることもまた否定できない事実である。
無門慧開は月林師観の会下で無字に参ずること六年、なかなか透過できず、睡魔が襲えば露柱に頭をぶつけて覚醒して無字三昧の工夫に決死の覚悟で取り組んだ。そして斎座(昼食)を知らせる太鼓の音声を聞いて忽ち自己の面目を徹見した。翌日、月林の室内に参じた無門は先師の二度の大喝に対して自らも大喝で応じ、「これより機鋒譲らず」とその語録の「告香普説」で述べている。「青天白日、一声の雷、大地の群生、眼豁開す。万象森羅、斉しく稽首す、須弥勃跳し三台を舞う」というその投機の偈は、痛快に見性した無門慧開の境涯を表してあまりある。
また南禅寺の創建開山である南院国師の嗣法の師である無学祖元も、その「告香普説」において「老僧十四にして径山(きんざん、万寿寺)に上り、十七歳にして発心して狗子無仏性の話に参ず。自ら一年を期して了当せんことを要す。竟(つい)に所解無し。又た做(な)すこと一年、亦た所解無し。更に做すこと三年、亦た所入無し。第五、六年に到って所入無しと雖然も、這(こ)の一箇の無字看熟し了って、夢裏にも也た看、遍天遍地ただ是一箇の無の字」という境地に到った。そして工夫純熟した挙げ句、身心が相離れて元に戻らず、同参のものが「彼は死んでしまった」というほど大死底の禅定に入った。そして首座寮前の板声を聞いて「本来の面目」を徹見し、歓喜に堪えず月下を走り出でて含暉亭に上って空を仰いで大笑していった、「大なる哉、法身、元来かくの如く広大なり」と。このとき無学祖元が先師無準師範に呈した投機の偈、「一槌に打破す、精霊窟、突出す、那吒の鉄面皮。両耳聾の如く、口唖の如し、等閒に触著すれば火星飛ぶ」もよく知られたものである。
無字の工夫の要点は、無門慧開が自らが刻苦して開悟した体験から、趙州無字の則で実に熱をこめて説いている通りである。およそ禅に参ずる者でこの無字の評唱を拝読しない者はあるまい。あとはそれをその通りに実践するかどうかにかかっている。真箇の三昧境に入得することができないのは「工夫、死地に入る」という真剣味がないからである。
公案工夫というものは、高峰原妙が「たとえ人がやってきて工夫中のお前の頭や手足を切り取り、お前の心臓や肝臓などの内臓を抉り、そのために命を失うようなことになろうが、断じて捨て去ってはならぬ。そのように工夫して初めていささか真実の工夫と呼ぶに値するといえる」(仮使、人有りて、你が頭を取り、你が手足を除き、你が心肝を剜り、乃至は命終るとも、誠に捨つべからず。遮裏に到りて方に少分の工夫を做すの気味有り)というほど凄まじいものである。
禅は実参実究である。そこで、最後に小衲の拙い工夫体験の一端をご紹介することにする。
建長寺で湊素堂老師に初めて参禅した日のことである。参禅を済ませて出口で拜をすると、老師は実に穏やかで謙虚な声でこう言われた、「私もあなたと同じ道を歩んでこの禅門に入った者です。もう一度生まれてきても、もう一度雲水修行をやりたいと思っております」と。そのお言葉を聞いた途端、野球のバットで殴られたような衝撃を受けた。背水の陣で臨んだ転錫の身の小衲は、間断なく公案工夫をしようと試みた。京叢林とは異なり、この僧堂の作務は半端ではなかったが、作務の最中でも必死になって無字三昧に取り組んだ。二人引きの大鋸(おおのこ)で大木を伐りながら、リズムに合わせて「無ー、無ー、無ー」と拈提して行くと、ゆくりなくも坐禅中よりも深い三昧境に入ることができた。茶礼の準備に赴いたところ、ちょうど出て来られた素堂老師にお目にかかった。その時老師はこちらを見て何か「ハッ」と感じられた気配がした。茶礼の際に三十人集まった雲水の中で突然名前を呼ばれ、小衲に目がけて茶礼のミカンを投げて寄越された。
小衲は卓越した古人のように何とかして真の無字三昧に入ろうとして、「臥薪嘗胆」の呉王夫差よろしく、草履や網代笠にも「無」と書き、一刻も「無」を忘れまいとした。建長寺僧堂では開枕後は裏山の墓地で十二時まで夜坐をしなければならなかったが、この強制的夜坐の時間はあまりよい坐禅はできなかったように思う。十二時になってからが、いよいよ自分の自由坐禅の時間である。小衲は由緒ある開山堂(昭堂)の建物の中の常夜燈を目の前にして、今度は誰にも気兼ねすることなく声を出して「無ー、無ー、無ー」と拈提して無字に死に切ろうとした。ふと気がつくと、一年上の先輩雲水が横に坐って一緒になって「無ー、無ー」とやっている。朝の開定は午前三時半であったから、三時には禅堂に戻り、そのまま単布団の上で坐禅するという日々が続いた。新到として臨んだ臘八大摂心では一週間殆ど眠ることなく、総警策以外の警策を一発も受けることがなかったが、前の道場では考えられない事態であった。今にして思えばよく身体がもったものであるが、当時はあまり疲れを感じることなく法悦の日々を送れたのは、公案三昧に打ち込んだせめてもの功徳であろうか。
公案工夫、無字三昧の境地は、知る人ぞ知る法悦の醍醐味である。禅に参ずる人はぜひとも「古人何人ぞ、われ何人ぞ」の覚悟で工夫に邁進して、未だ曾て体験したことのない大歓喜を得て頂きたいものである。