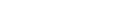「自然治癒力」(月刊コラム【No.99】2011年9月)
光雲寺では先般の東福門院三百年御忌・晋山式に向けて数年がかりで前庭と中庭を中心とした境内整備をおこなってきた。とりわけ植治(七代目小川治兵衛)作庭の京都市指定名勝庭園である中庭は、「植治の庭」の最高権威であられる尼崎博正先生や京都市の文化財保護課の専門職員の方を中心とした修復会議を幾度となく開き、京都市から推薦された造園業者に依頼して池の護岸を伝統的な版築の技法により全面的に改修し、植治作庭当時の資料を参考にして、植栽をして杉苔も広く植え、面目を一新することができた。法要に参列された大方尊宿(管長・老師)方が異口同音に庭と風致とを賞賛されたというのを伝え聞き、潤沢ではない財政事情の中で思い切って改修に踏み切った甲斐があったと喜んだものである。
ところがそれから一ヶ月ほど経つうちに、新たに植えられた杉苔に直径20-30センチの円形状の枯れたような茶色の箇所があちこちに表れ、その数が次第に増えていった。尼崎先生の推薦により普段から光雲寺の庭木の手入れをしてもらっている熟練した庭師さんがこれを見て、施工した造園業者と庭園設計士と京都市文化財保護課とに連絡をしてくれた。
しばらくして庭園設計士が「光雲寺庭園 苔の調査報告書」を作成したのを受けて会合がもたれたが、その報告書では、「この造園業者が同じ苔を使って施工した他の庭園などを調査した結果、同様の症状は認められず、京都市内で同様の症状が現れている庭園は確認されなかった」という理由で、「光雲寺独自の症状の可能性が高いと考えられる」と結論づけていた。要するに、「光雲寺の環境に問題があったために起こったことであるから、施工した造園業者や庭園設計士にはいささかの責任もない」と言いたかったのであろう。光雲寺住職である小衲は、「しかしこの光雲寺でもこの施工が行われる以前にはこんなことが起きなかった」と言った上で、「とはいえ、こういう特殊な症状が現れたということは恰好の良い勉強になるではないですか」と破顔微笑すると、一座に安堵の空気が流れたのには失笑せざるをえなかった。
相手に全面的に責任を負わせて修復を迫るつもりは毛頭なかったが、確実に言えることは、自己弁護のみに終始するこうした不誠実な対応をとる造園業者や庭園設計士には金輪際もう仕事を依頼することはないということである。この修復の中心となって長期間にわたり活動した庭師は、「私は修復後に来たのは今回が初めてです」と言って恥じ入るところはなかった。自分が精魂込めてやり遂げた仕事であるならば、アフターケアも心がこもっていて然るべきであろう。やはり小衲が「彼は20年の経験があるというが、あてにならぬ」と修復の最中から見抜いていた通りであった。
結局は熟練した庭師さんが予想したように、高温多湿によりカビが苔に発生したことが今回の丸く赤茶けて枯れる原因であることが分かり、園芸会社などからの情報により、かの設計士と造園業者は対処方法として、ベンレート、ボトキラーなどの微生物防除剤の散布を薦めてきた(もちろん費用はすべて光雲寺もちという積もりであろう。呵々)。しかし熟練した庭師さんが、「薬剤をひとたび撒くと、中途でやめれば逆効果になり、続けて撒かずにはいられなくなります。薬など撒かずとも赤茶けた苔が枯れることはないそうです」というのを聞いて、薬剤を使用するのを控えることを即断した。その結果、二ヶ月ほど経った現在では赤茶けた苔の間から緑の新芽がちらほらと出てくるようになった。苔の自然治癒力を信じたお蔭である。
これが薦められるが如く薬剤を散布していたらどうなったであろうか。結果はいうまでもなく、人為的な対処療法により苔がますます弱っていき、抜き差しならぬ事態に至ったであろうことは想像に難くない。それはちょうどわれわれ人間についても言えることである。たとえば風邪を引いたからといって、病院に行ったり闇雲に薬を飲むのは感心したことではないそうである。「病気になれば薬を飲み病院へ行く」ということがわれわれの一般常識として定着している感があるが、船瀬俊介氏が明らかにした衝撃的な報告によれば、1973年にイスラエルで病院ストが1ヶ月実行された際には、診察可能な患者の数が9割以上も激減し、その結果、何と死亡率が半減し、ストが解除されたらまた元の死亡率に戻ったということである。つまり病院は患者を治癒するところではなく、病人を作り出し、患者を殺す機関であったのである。
小衲のところには良くうつ病のひとが来られる。例外なく病院で薬を処方してもらっているものの、それでは悪化する一方で、良くなったためしはない。小衲のところでうつ病の方が劇的に改善するのは、そのひとを病人と見なさずに本来もっている自然治癒力を発揮できるようにするためであろう。ただしどのように対処するかのマニュアルなどなく、臨機応変であるといってよい。今は亡き俳優の児玉清さんが、何年か前に南禅寺の夏期講座の講師として招かれ、小衲も親しくお話をする機会があった。人柄は想像したとおりの爽やかなお方であったが、「うつ病のひとに薬の処方は無用どころか、かえって有害である」という点で意気投合したという思い出がある。
とりわけガンに関しては、20兆円ともいわれるガンからみの利権をむさぼる医者や製薬会社のせいで、一体何人の人たちが命を落とされているであろうか。船瀬俊介氏によれば、年間少なくとも26万人のガン患者が治療の名のもとに殺されているという。前立腺ガンになり医者の再三の薦めを信じて抗がん剤を受け容れ、すさまじいばかりの薬害のせいで遷化した小衲の弟もその一人である。「手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りないこの世の息が」という歌を残して昨年の8月に亡くなられた京都在住の歌人であった河野裕子さんの、ご主人との共著の『たとへば君』(文藝春秋刊)には、このすぐれた歌人の、闘病というよりはむしろ抗がん剤治療との壮絶なまでの格闘の記録が含まれている。「病気のほんとうの怖さを知ったのは化学療法に入ってからである。癌は副作用との闘いであるといわれているがまことにその通りである」と述懐され(230頁)、「薬害に正気を無くししわれの傍に白湯つぎくれる家族が居りき」と詠んでおられる(200頁)。ご主人はご主人で、「副作用はもとより承知しかれどももう止めようと言へるはずもない」と苦境を吐露されている(238頁)。
抗がん剤の副作用を我慢しても治癒すればまだしも、かえって有害で免疫力が低下して死に至ることになる。800人の患者に手術と抗がん剤を施した或る医者は、「だれ一人生きていません。だから現代のがん治療は無力とハッキリ言えます・・・」と告白している(船瀬俊介著『病院へ行かずに「治す」ガン療法』花伝社、237頁)。それでも多くの人が「手術・放射線・抗がん剤」の三大療法を盲信しているのは、自らの内なる自然治癒力の絶大な力を知ることが少ないためである。「自然治癒力」なる言葉は医学事典にも見当たらないそうであるが、そんなことで治ることが白日の下にさらされれば、医者が「商売あがったり」になるからである。
その一方で、数千人もの患者を抗がん剤や化学療法で殺してきた東大病院の4人の教授たちが、自分たちががんになったら断じて抗がん剤治療などを拒否し、食餌療法により治癒してぴんぴんしているというが、実にけしからぬ話ではないか。彼らはかの三大療法が決してガン患者を治癒できるものではなく、かえって命を奪う危険が多分にあることを臨床経験上よく知っているのに、それを平気で患者に投与しているのである。医者の99%は自分や家族に対しては決して抗がん剤などを使用しないというのはよく知られている事実である。詳細は、安保徹著『新がん革命』(ヒカルランド)や船瀬俊介著『病院へ行かずに「治す」ガン療法』(花伝社)をご覧頂きたい。
多くの方々が自らの内なる自然治癒力を信じて如何なる精神的・身体的状況に陥ったとしても前向きに生きて行かれることを切に願うものである。
(なおこの光雲寺ではお寺に滞在して禅の修行をする人を募集しております。出家希望者を優先しますが、在家の方でも可能です。年齢は問いませんが、男性に限らせて頂きます。ご希望の方は光雲寺の方にご連絡下さい。℡075-751-7949)。