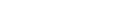「160年前の下宿生」2025年07月【No.263】
先月中旬のことです。夕方になって前庭の池の鯉に餌をやろうと出て行くと、門前に4,5名の方々がおられて、「墓参に来ました」ということでした。聞けば、そのご先祖は、光雲寺に下宿されていて、160年前の元治二年(1865)に20歳で亡くなられたということです。江戸時代からの過去帳にもしかしたら記載されているかもしれないと思い、過去帳を持参して調べたところ、確かに記載されており、墓参に来られた方々は感激しておられました。ただ何分にも檀家さんのお通夜が差し迫っていましたので、立ち話だけでお帰りになりました。上がって頂いて客間でお抹茶でも差し上げる時間があれば、ゆっくりお話しできたかと思います。
頂いた資料をあとで拝見すると、亡くなられた方は肥後細川藩士の徳永左右之助(そうのすけ)・龍虎という方で、弘化三年(1846)熊本県のお生まれで、万延元年15歳の時に浦賀に来航した異国船退治のための大筒手(おおづつしゅ)の一員として相模(さがみ)国に赴いたということです。これはおそらくはペリー一行の来航を指すものでしょう。
文久四年(1864)の19歳の時に京都警護の守護、御備頭(おんそなえがしら)、大筒先手(大筒を使用して先手として先に立って戦う部隊)の一員として上京したということです。最初は正願寺(真宗か?)というお寺に止宿していたそうですが、御陣上宿替え(ごじんうわやどがえ)により、鹿ケ谷の光雲寺に移られたということです。ところが12月21日より風邪気味となり、疱瘡(天然痘)を患(わずら)い、元治二年(1865)の1月1日に養生かなわず病死し光雲寺に埋葬されたということです。墓石も現存しており、戒名は「釋徳宝」と記録されております。
後日、古い過去帳を調べてみると、元治元年には何と6人もの肥後熊本藩士が光雲寺で亡くなっているという記録がありました。他の5人の死因は記録されておりません。光雲寺は徳川2代将軍秀忠公のご息女であられた東福門院様(御水尾天皇の皇后)がご自分の菩提寺として、大阪の四天王寺付近から移転再興されたお寺ですから、徳川幕府方の熊本藩士が多く止宿していたものと思われます。それにしても幕末の動乱期の状況を彷彿とさせる記載に痛感せざるを得ない思いが致しました。
墓参の方々が帰られたあとで、光雲寺に下宿している4人の学生さんに対して、「君たちの160年前の先輩がいたぞ」と事情を説明すると、彼らはとても驚いていました。ただ、墓参の方々とゆっくりお話しする時間がなく、連絡先などを聞いていなかったのが心残りです。もしその折の方がこのコラムをご覧になられたら、ぜひご一報頂きたいものです。