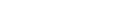「温故知新」2014年4月【No.130】
先月のコラムで「温故知新」の必要性に言及したが、その後、かく申すわが身がまだまだ「温故知新」の足りないことを痛感する体験に出くわしたことを、何かのご参考になればと思い、お話し申し上げたい。
まず最初は、東京在住の或る知り合いの方からのメールで、その方の遠縁に当たる石光真清(まきよ)氏の『城下の人、曠野の花、望郷の歌、誰のために』(石光真清の手記 全4冊 中公文庫)という厖大な手記が刊行されていることを知り、興味をもって早速取り寄せて拝読したのである。石光真清氏は明治元年(1867)に熊本に生まれ、少年時代を神風連や西南戦争の動乱のただ中で過ごし、陸軍の軍人となって日清、日露の戦役に参加したが、大正六年(1917)のロシア革命後に諜報活動の必要性を感じ、再びシベリアに渡り、諜報活動に従事し、昭和十七年(1942)に76歳で逝去した。
その晩年は夫人の死や負債などで失意の日々を送られたようで、決して順風満帆の人生とはいえないが、その手記にはフィクションである小説にはない実体験の迫力と説得力がある。毎日出版文化賞を受賞したのもむべなるかなと思える。神風連の乱や、鎮台が置かれていた熊本城をめぐる官軍と西郷さんの薩摩軍との攻防の最中(さなか)に垣間見える、敵味方を越えた当時の人々の心根(こころね)の気高さにはつくづく感心させられる。
たとえば、明治九年(1876)に熊本市で起こった明治政府に対する士族の反乱である神風連の乱に際して、神風連の領袖である加屋霽堅(かやはるかた)に出逢い、加藤清正公に関する逸話を滔々(とうとう)と語るその風格と赤心に触れて、心酔した石光真清氏が手柄顔でその話をしたところ、進歩的思想の持ち主であった母や洋学生の兄や従兄がそろって氏を冷笑した。するとそれまでこの有様を黙って眺めていた父は、「お前たちは、神風連、神風連と、あの方々を、天下の大勢に暗い頑迷な人のようにいうが、それは大変な誤りだ」と、穏やかながらも、きつい目付きでひとわたり皆を見回していった。
「あの方たちは、御一新前は熊本藩の中枢にあって、藩政に大きな功労のあった方々だ。学識もあり、勤王の志も厚い。ところが御一新後の世の動きは、目まぐるしく総てが欧米化して、日本古来の美点が崩れていくので、これでは国家の前途が危ないと心配し、・・・百七十余名の方々が会合して今後の方針を協議された。この会合で、日本古来の伝統は必ず護る、外国に対しては強く正しく国の体面を保つことを申し合わせた。この人々を進歩派の人たちが神風連と呼ぶことになったもので、その後、いろいろと保守の策を試みたが、時代の風潮を阻むことは出来なかった。この上は神明の力によって世論の挽回を図るほかに道はないと、党人は神社神社に参拝して・・・祈りを捧げた。忠操の凄烈、素行の端正、神風連の党人は実に立派な人格者ばかりだ。・・・お前たちが洋学をやるにしても、あの方々の立派な人格を見習い、日本人としての魂を忘れない心掛けが大切だ。・・・いいかな。今後はあの方々を軽蔑するようなことは慎みなさい」。(『城下の人』26―28頁)
石光真清氏の父君のこの訓誡はまさに正論である。その証拠に母も兄も従兄も反論できずに、叱られた生徒のように膝に目を落として黙っていたという。威厳を以て正論を述べる父君に三人が圧倒された有様が目に見えるようである。
また西南戦争に際し、薩摩軍の侵入に備えて鎮台が加藤清正公建立の熊本城を初めとして城下のほとんどを焼き払い見渡す限りの焦土と化したというのは、驚くべき事実である。谷干城(たにたてき)や樺山資紀(かばやますけのり)や児玉源太郎などという傑物が統率していたにもかかわらず、何故にそのような挙に出たのか、いぶかしい限りである。
興味深いのは官軍・薩軍ともに或る種の余裕を持って戦に臨んでいる点である。西郷隆盛を筆頭とする薩軍は薩摩隼人と呼ばれる戦のプロの武士集団である。それに対して鎮台兵は農民や商人などの成り上がりの素人集団である。薩摩兵は「なかなか鎮台兵も強く、われわれの考えは根本から覆された。何の教育も受けない若者どもも、鋤鍬(すきくわ)、そろばんに代えて銃を執れば、立派な武士となり、われわれや熊本武士を向こうに廻して見事に戦う。日本も末頼もしいことだ」と鎮台側を盛んに賞賛したという。
石光真清氏のこの手記にはこの様にいろんな興味深い記述がある。関心がある方はご一読をお勧めしたい。
また、光雲寺中興の英中玄賢禅師と親交のあった板倉重矩公(しげのりこう)の光雲寺宛の直筆の書状を何年か前にさる方から進呈して頂いたが、その後その重矩公の事蹟を知りたく思い、幕末から維新にかけて著述され、明治初めに刊行された『名将言行録』を取り寄せて読んだところ、驚嘆すべき名将の言行をいくらも知ることが出来た。
例えば、現在NHKの大河ドラマで放映中の黒田官兵衛(如水)である。官兵衛はかつて「家康を攻め滅ぼし天下を取ろうと思えば、それはいともたやすいことだ」と公言するほど、軍略に長けていたが、その彼が「文武両道」について語った一段がある。
彼はいう、「大将が文道を好むというのは、必ずしも書を多く読み、詩を作り、故事を覚えて、文字をたしなむことではない。まことの道を求め、諸事についてよく吟味工夫をし、筋目を違えず、間違ったことのないようにして、善悪をただし、賞罰をはっきりし、憐れみ深くすることをいうのだ。また大将が武道を好むというのは、もっぱら武芸を好んで、心がいかつくなることをいうのではない。戦の道を知って、常に乱を鎮める知略をもち、武勇の道に志して、油断なく士卒を調練し、武功ある者には恩賞を与え、罪のある者には刑罰を施して剛気と臆病とを見分け、無事な時でも合戦を忘れないことをいうのである。武芸をもっぱら好んで、自分一人の目立つ働きをしようというのは匹夫の勇で、これは小身者の嗜(たしな)みであり、大将の道ではない」。
最後に太閤秀吉の信長評をご披露したい。秀吉公はいう、「信長公は勇将であるが良将ではない。剛をもって柔に勝つことを知ってはおられたが、柔が剛を制することをご存じなかった。ひとたび敵対した者に対しては、その憤りがいつまでも解けず、ことごとくその根を断ち葉を枯らそうとされた。だから降伏する者を誅戮(ちゅうりく)し、敵(かたき)打ちは絶えることがなかった。これは人物器量が狭いためである。人には敬遠されるが、衆からは愛されない。たとえば虎狼のようなものだ。咬まれることを恐れはするが、見る者はそれを殺して、その害を免れようとする。これが明智の謀反を起こさせたのだ」。
秀吉公が主君であった信長のことを「人物器量が狭く、虎狼のようだ」と形容していることを一体何人の人がご存知だろうか。秀吉公はその反省の上に立って弊を改め、人心を掌握して天下を平定するに到ったのである。天正十年、信長が武田氏を滅ぼした時、毛利攻めで中国地方にいた秀吉は、勝頼が死んで甲斐が平定されたと伝え聞き、大息し、「勝頼のような人を殺したのは惜しいことだ。わしがもし軍中にいたなら、強いて諫めて勝頼に甲斐と信濃の二州を与え、関東の先陣としたとすれば、東国はたちまち押しまくれたものを」と繰り返し悔やんだという。
独創的哲学者であり、熱心な禅の参究者でもあった西田幾多郎博士は、「日本人の真髄を知りたければ『常山紀談』を読むように」といわれたという話を以前読んだ記憶がある。『常山紀談』はいうまでもなく江戸時代中期に儒学者・湯浅常山により著された戦国武将の逸話集である。伊藤博文や大隈重信などは『名将言行録』を熟読玩味したといわれる。われわれ日本人が学ぶべき宝物の如き古人の高邁な言行は、まだまだ無尽蔵に残されているというべきである。