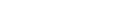「神沢杜口の『翁草』」2022年11月【No.232】
江戸時代に神沢杜口(かんざわとこう)(宝永七年―寛政七年、1710−1795)が書いた『翁草』(おきなぐさ)はとても興味深い本です。この書物の原文は『日本随筆大成』に入っておりますが、なにぶん全200巻の大部のものですので、なかなか全体を読み通すことは難しいと思います。教育社から出ている『原本現代訳』という抄訳もありますが、どうも肝心かなめな箇所が網羅されているとは言えない気がします。その点、立川昭二氏の『足るを知る生き方 ―神沢杜口「翁草」に学ぶ』という本は、杜口を「人生の達人」と敬慕する立川氏が心を込めて書かれた好著だと思います。今回久しぶりに読み返してみて、その感を一層深くしました。
杜口の前半生は京都町奉行所の与力という中間管理職であり、役所勤めの後半は旗本たちを監察する「目付(めつけ)」という上級管理職でした。彼はこの要職を勤めるに際して「陰(かげ)の慎み」として、勤務中の慎みだけではなく、勤務外も謡曲・俳諧・囲碁などの趣味を持ち、気分転換をして気を養いました。これは仕事にあまり心を使いすぎて、心身共に不調になることを用心したためです。
杜口のみならず、江戸時代の人たちの多くが抱いていた願いは、若い時に苦労して真面目に働き、老年になってから楽しく過ごすということでした。杜口は四十歳ごろに病弱を理由に退職し、八十六歳で亡くなるまで自分の好きな文筆の道に入り、江戸時代の一級の資料といわれる『翁草』二百巻の大著を完成しました。実はこれを百巻まで書き終えたところで、七十九歳の杜口は京都市中をほとんど焼け野原にした天明の大火に遭遇して、先祖伝来の家宝もろとも、この心血を注いだ草稿を焼失してしまったのです。
普通の人ならこれで落胆して無気力になるところでしょうが、晩年に到るまで一日20キロ以上を歩いて体力を養っていたという杜口は、大火で焼失した市中を見て回り、詳細な地図を書いたのです。立川氏の前述書の見開きには杜口手書きの焼失地図が掲載されています。そしてその後に二百巻の『翁草』を完成させたというから、感服のほかありません。
杜口は与力の入り婿として家付き娘と結婚して五人の子供をもうけたのですが、四十四歳で妻を亡くしてから独身を通しました。子供も四人が亡くなり、末娘が婿養子をとって家を継いだのですが、三人生まれた孫も二人が亡くなりました。普通ならこの娘一家と暮らすでしょうが、杜口は老いて家族に執着して疎(うと)んぜられることを危惧して独り暮らしを選びました。「尋常(よのつね)の人はこれを掌(たなごころ)の玉として、愛迷う習いなれども、われはそのきずなを離れて他人あしらいなり」といい、家族と離れて、ときどき逢う方が、「遠いが花の香り」で互いに「うれしき心地」がするものだと達観していたのです。
杜口は一人暮らしの四十二年の間に、何と十八回も転居したというから驚きです。杜口が好んで立ち寄っていた紅葉で有名な永観堂は私の自坊の光雲寺の至近距離にあるので、矍鑠(かくしゃく)とした老杜口が永観堂門前の鹿ケ谷通りを歩いていたかと想像するのも楽しい気がします。「体調がすぐれない人は、気分を安らかにして雑念を払って歩けばよい。これを続ければ、薬を使うよりもはるかに効果がある」という杜口の言葉は、現代のわれわれにも参考になる言葉です。
『翁草』には江戸時代の武士や町人などの興味深い逸話が沢山書かれております。遠島の島流しにあった父の介抱に遠島行きを申し出た十二歳の少年の話や、信州の十一歳の少年が狼に襲われた父親を救うために命がけで狼と戦って父を救い、それを代官所が上申したところ、江戸幕府で評議されて、白銀二十枚が下された話などがのっております。
これから秋の夜長にゆったりとした気持ちで『翁草』を読まれたら、きっと気分爽快になることを請け合うものです。とりあえずは立川氏の著書を読まれんことをお勧め申し上げます。