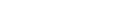「大安楽」( 月刊コラム【No.81】2010年2月 )
龍牙居遁(りゅうげきょとん)禅師という、中国唐代の名僧がいる。曹洞宗の開祖である洞山良价の法を嗣いだ禅僧であり、臨済禅師との問答も残っていることは、少し禅に触れた人ならばご存じであろう。
江戸時代の禅籍である『鉄笛倒吹』(てってきとうすい)の第二十八則に「龍牙古休」の話がある。「龍牙遁禅師、因みに僧問う、古人、箇の甚麽(なに)を得て便ち休し去る。牙曰く、賊の空室に入るが如し」(龍牙遁禅師にある僧が質問した、「古人は一体なんの道理をを得て大安楽の境地に至ったのでしょうか」。龍牙が答えた、「ちょうど盗賊が空室に入ったようなものだ」。)
この僧の問いに対する風外禅師の、「汝、什麽(なに)を得てか、恁麽(いんも)に休せざる」(かくいうお前は、一体なにを得てそんなに心安らかならずに質問するのか)という下語(あぎょ、禅的ヤジ)が面白い。これが下語の妙味である。龍牙の「賊の空室に入るが如し」に対しては、風外は「ただおそらくこの僧はこの空室という宝を捨て去ることができないであろう」と下語している。
盗賊が空室に入ることが、どうして大安楽につながるのか。また空室がどうして宝物といえるのか。しかもこの宝を捨て去らねばならぬとは、一体どういうことか。
盗賊は部屋の中にはさぞかし素晴らしい宝物があるに相違ないと思って進入するのだが、しかし期待に反して何もない空き家であった。修行に骨を折って悟れば必ずや目を見はるような境地に至るに相違ないと思いこんでいた者(盗人根性のある修行者)が、現に悟ってみれば、これといって所得はなく、本来無一物であることを知り、求め回る心がやんだのがちょうど同じようなことであると龍牙はいうのである。
この則に対する奥龍禅師の偈頌は格調高いものである。「幾たびか剣刃上に之(ゆ)き、また曾て薄氷を履んで猜(うたが)う。入得すれば是れ空室、偸心(ちゅうしん)死して灰となる。帰り来たって晨夕(しんせき)分に随って送れば、恰(あたか)も平地に徘徊を打するに似たり。清風明月、何の極まりか有らん。自家の宝蔵、ここに到って開く」(何度も剣の刃の上を歩くような苦難を重ね、また目指す境地をいろいろと推量して、薄氷を履む思いで疑った時節もあった。だが、悟入してみれば、空き部屋に入ったようなもので、所得とすべき一物もない。かくして、何とかして悟ってやろうなどという妄想分別は灰の如くに消え失せてしまった。そうした境地になれば、ただ腹がへれば飯を食らい、疲れたら眠るという、何らの造作も計らいもない淡々とした毎日である。悟ったならば思う存分に衆生済度をしようと思っていたが、悟ってみれば迷える衆生というのも見あたらない。自分自身も本来無一物(空)という宝物であることが分かった。)
臨済禅の修行では一則の公案に取り組んで、文字通り目の色を変えて工夫三昧になることが求められる。といっても、師家がいくら力説しても、やるか否かは本人にかかっている。自分の境地を顧みることなく、また悟りすらも求めることなく、四六時中ひたすら馬鹿になって真一文字に工夫を続けていると、知らず知らずの間に分別がこそげ落ち、八面玲瓏となってえもいえぬ法悦の境地が現前してくるから面白い。たとえ短時間でも真剣に工夫すれば、ただちに佳境に入ることが可能である。
禅の修行を格別にする人でなくても、あれこれ悔やんだり先のことを取り越し苦労したりせずに、眼前のことに心を込めて対処していれば、そのうちに道が開けるものである。たとえ不遇であっても、不満の念を起こさず、足るを知って日々を楽しんで過ごす人に、憂いの起こりようはない。
安楽の道がこの方向にあるということをお話すると、たちまち見違えるように顔を輝かせる人がほとんどである。どうかご自分の中にこそ真の宝物があるということを信じて、自信をもって生活して頂きたいものである。