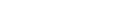玄賓僧都
最初に採り上げるのは、鴨長明の『発心集』の冒頭に載せられている玄賓僧都(げんびんそうず)である。千二百年のその昔、名利を離れてひたすら仏道に精進された僧都の気高い行履(あんり)は、同時代の人に鑽仰(さんぎょう)されたばかりか、後世の宗教者の模範となってきた。
『発心集』と玄賓僧都
『方丈記』の著者として有名な鴨長明の著作に、『発心集(ほっしんしゅう)』なる書がある。この書は、長明が自らの反省と修養のために、日本の国内の出来事で「発心」1に関して自分が見聞したことをまとめたものである。彼は、その「序」において、「生死を離れて早く浄土に生まれん」ことを目標として、「わが発心の一念を楽しむばかり」と著述の意図を述べている。もっとも、『発心集』とは題されてはいるものの、必ずしも真実の菩提心を発(おこ)した者ばかりではなく、名聞(みょうもん)のためにお堂を建てた結果、天狗になってしまったという不心得(ふこころえ)な上人のことなども記載されている。
この書はこれまで主として、文学研究者によって学問研究の対象とされることはあっても、道心を興すという著作本来の目的に即して、少なくとも表向きには読まれてこなかったように思われる。
そして、この書の冒頭に載せられているのが、外ならぬ玄賓僧都である。(『発心集』では「玄敏」と表記されているが、ここでは一般に行なわれている表記に従って、「玄賓」と表わすことにする。また、以下の引用や解釈は、三木紀人校注『方丈記 発心集』〔新潮日本古典集成、新潮社版〕に拠るものである。)
玄賓僧都に関して、『発心集』は、「一、玄賓僧都、遁世逐電の事」と「二、同人、伊賀の国郡司に仕はれ給ふ事」という二段に分けて述べている。ここでは先ず私見を雑えることなく、『発心集』記載の文章を、多少の解説を加味しながら忠実に訳出してみよう。
「玄賓僧都、遁世逐電の事」
昔、玄賓僧都という人がいた。山階寺(やましなでら:興福寺の旧称)の貴い名僧(知者)であったが、俗世を厭(いと)う心が深かったので、俗心にまみれた他の僧侶との交わりを好まなかった。そのため、三輪川(初瀬川の桜井市三輪辺りを流れる部分の呼称で、清流で知られる)のほとりに、ささやかな草庵を結んで瞑想にふけって隠棲していた。桓武天皇の御代(みよ)に、玄賓僧都の高潔な生き方を聞いて感動された天皇は、無理を承知で召し出されたので、僧都もついに遁れるすべがなく、致し方なく参上した。(延暦二十年〔805〕、桓武天皇は今の鳥取県西部・伯耆〔ほうき〕の国にいた玄賓僧都を請〔しょう〕じ、伝燈大法師位を授けた。)
しかしながら、やはり本意ではないと思われたのであろうか、玄賓僧都は、平城(へいぜい)天皇の御代に大僧都に昇進させようとされたのを辞退して、次の歌を詠まれた(『和漢朗詠集』下、所載)。
「三輪川の清き流れにすすぎてし、衣の袖をまたはけがさじ」
(三輪山のあたりに隠棲して、俗世間や俗僧と交わることなく、三輪川の清き流れでせっかく綺麗に洗い清めた、僧侶としての本来の生き方を、いかに天皇の思〔おぼ〕し召しとはいえ、名利のためにけがすことはできませぬ。)
そうこうするうちに、玄賓僧都は、弟子にも召使いにも知られずに、いずこともなく出奔(しゅっぽん)してしまわれた。心当たりのある場所を探してはみたが、僧都の行方(ゆくえ)は分からなかった。捜索の甲斐なく何日も経過したが、僧都の身近で暮らしていた人はもとより、多くの人から慕われていた名僧の思いがけない出奔を、世間の人すべてが嘆き悲しんだ。
その後、年月を経て、僧都の弟子であった人が、所用で北陸の方へ行く道中で、或る所に大きな川があった。渡し舟が来るのを待って乗ったところ、その渡し守を見れば、頭の髪がつかめるほどまで生えた法師で、薄汚い麻の粗末な衣を着た人であった。
「異様な風体だな」と見ていたが、やはり見覚えのある気がしたので、「誰がこの人に似ていようか」と思い巡(めぐ)らすうちに、出奔して何年にもなる自分の師匠の玄賓僧都ではないかと考えるに至った。「こんなみすぼらしい身なりとは、もしかして人違いではないか」とは思っては見たが、いささかも疑うべくもなかった。件(くだん)の弟子は、師匠のこの哀れな有様を見て大層悲しくなり、涙のこぼれるのを押さえつつ、何気(なにげ)ない振りを装っていた。
渡し守の法師の方も、どうやら気付いている様子ではあったが、ことさら視線を合わせようとはしない。弟子は、走り寄って、「なぜこんな所においでなのですか」とでも言いたかったのであるが、大勢の客が乗船していたので、「かえって人目については具合が悪かろう。都への帰り道に、夜分おられる場所に訪ねて行って、ゆっくりとご挨拶することにしよう」と考えて、そのままやり過ごした。
こうして、帰途にその渡しに行ってみれば、別の渡し守に変わっていた。目の前が真っ暗になり、胸がふさがって、詳細を尋ねれば、「その法師はおりました。何年もここの渡し守をしておりましたが、そうした身分の低い僧に似合わず、常に心を澄まして念仏ばかりを申し、船賃をあれこれ取ることもなく、ただその日に食べるものなどの他は、物に貪欲(どんよく)な心もないような有様でしたので、この里の人も大層好感を寄せておりましたところ、どういう訳かは存じませんが、先頃かき消すように突然姿をくらまして、行方しれずとなったのでございます」と語るのを聞いて、くやしく、どうしようもなく残念に思い、行方不明になった月日を数えれば、ちょうど自分がお目にかかった時であった。僧都は、わが身の所在が知られたと思い、また去ってしまったに相違ない。
鴨長明は、この段の末尾に、彼とほぼ同時代人である三井寺(園城寺)の道顕(どうけん)僧都(文治五年、1189年寂、享年五十五歳)という人が、古(いにしえ)の玄賓僧都のこの物語を読んで、感激のあまり涙を流しつつ、「渡し守こそ、まことに罪なくて世の中を渡る道であろう」と言って、琵琶湖に舟をひとつ用意したことを紹介している。
そして、渡し守になりたいという道顕僧都のこの希望はかなえられることなく計画倒れに終わり、舟は琵琶湖に注ぐ瀬田川の河岸にそのまま朽ちてしまったものの、名利を離れて渡し守をしようとしたその志は、やはり尊いものであった、と結んでいる。
「同人(玄賓僧都)が伊賀の国の郡司に仕えられた事」
この段は、前段でまたまた失踪した玄賓僧都の後日談である。ここでも長明の記述に即して訳出することにする。伊賀の国(三重県北西部)の或る郡司(国司の下で、郡を治める役人)のもとに、見苦しい容体の法師が、「雇って頂けませんか」と言って不意に入って来た。主(あるじ)はこれを見て、「和尚さんのような方を置いても、何の役にも立ちませぬ」と言った。
その法師が、「法師と申しても、私のような者は普通の下男と何ら変わりませぬ。どういう仕事でも、この身でできることは致しましょう」と言うので、主も「それならよかろう」といって置くことにした。法師は喜んで、大層真心を尽くして働いたので、主は自分がとりわけ大切にしていた馬を法師に預けて世話をさせた。
こうして三年ばかりが経ったが、この主の男は国の長官に対していささか具合の悪いことをしでかし、国外追放されることになった。(郡司は終身官で世襲制であったので)郡司の父や祖父の時から住み着いていたので、所領も多く、一族郎党も多かった。
他国へさまよい行くことは、いずれにせよ大変な悲嘆であるには違いなかったが、遁れるすべもなく泣く泣く出立するのを見て、あの法師が或る者に向かって、「ここの殿に一体どういう困ったことが出来たのですか」と問うと、「お前のような下賎の者が理由などを聞いてもどうしようもあるまい」とけんもほろろに答えたので、法師は、「どうして身分が低くても関係ないはずがありましょうか。ご主人としてお仕えして、もう何年にもなるのです。差別されるのはおかしいです」と言って熱心に尋ねたので、男も事の次第をありのままに語った。
法師は言った、「私が申し上げることを必ずしもお取り上げにはなりますまいが、どうしてそう急いで国を去ることがありましょうか。物事には意外な成り行きもあることですから、ここはひとまず都に上り、何度となくこちらの事情を申し述べて、それでもなお致し方なければ、その時はいずこなりとも行かれればよろしいのではございませぬか。私がいささか存じ上げている人が、国司の近辺におられます。お尋ねして申し上げてみましょう」と。
法師の思いがけない言葉に、人々は、「(見かけによらず)すごいことを言ったものだな」と怪訝(けげん)に思って、主である郡司にこの経緯(いきさつ)を語ると、主は法師を自分のところに呼び寄せて、自ら問い質(ただ)して話を聞いた。法師の言うところを全面的に頼りにしていた訳ではないが、他にあてもないので、この法師を伴って京に上(のぼ)ったのである。
その当時、この国は、大納言某(なにがし)が国司として治めていたのであるが、京に辿り着いて大納言の住まい近くまで行ってから、法師が、「人をお訪ねしようというのに、この身なりでは何とも異様なので、衣と袈裟(けさ)を探して頂けませんか」と言ったので、借りて着せた。
主の男と同道して、彼を門口に待たせ、大納言の邸内に入って、法師は「申し上げたいことがございます」と声を上げた。その場に大勢集まっていた人々は、声の主(ぬし)を見て、一斉(いっせい)に地面にひざまづき敬うのを見て、伊賀の郡司は門のそばからこれを見ていて、驚くまいことか、「何ということだ」と目を見張って成り行きを見守るばかりであった。
すぐにこれを聞いて、大納言が急いで出てきて対面し、上を下にも置かぬもてなし振りは、格別であった。大納言は、「それにしてもまあ、貴方様がどうされたのかと想像する手掛りすらないままに月日が過ぎておりましたのに、まぎれもないご本人がお越しになるとは」などと言って、思いのたけをしきりに述べ立てた。
それに対して、玄賓僧都は言葉少なに、「そのようなことはいずれごゆっくりとお話し致しましょう。今日は特別申し上げたいことがあって参った次第です。伊賀の国で、ここ何年も私がお世話になっているお方が、思いがけずにお咎(とが)めを蒙(こうむ)り、国を追われるということで、歎いておられるのです。まことにお気の毒に思いますので、もしさほど重い罪でなければ、この法師に免じてお許し願えないでしょうか」と言った。
大納言は、「あれこれ申し上げるべきことはございませぬ。貴方様がそのように好意を持っておられる者ならば、処罰されずともわが身で自分の過ちを自覚できる男でありましょう」と言って、僧都の求めに応じて、かの郡司をこれまで以上に厚遇する内容の、喜ぶべき庁宣(ちょうぜん、在京国司が出す命令書)を快く出してくれた。伊賀の郡司がこの有様を蔭で見ていて、呆気(あっけ)にとられるばかりであったのは当然のことである。
色々と考えたが、郡司はあまりのことにかえって然るべきお礼の言葉も出なかった。「宿に戻ってゆっくりとお礼申し上げよう」と思っていたところ、玄賓僧都は、衣と袈裟の上に例の庁宣を置いたまま、さっと立ち出ずるように出て行き、そのままどこへともなく姿を隠したということである。
ここまで書いてきて、鴨長明は、「これもかの玄賓僧都のされたことである。まことに比類なく尊い(有難い)お心持ちであったというべきであろう」と、この段を結んでいる。
玄賓僧都の気韻
玄賓僧都の逸話は、もとより『発心集』のみならず、『古事談』、『三国伝記』など中世の仏教説話の類いに頻出する。ただ、自著の冒頭に掲げたことで、長明が如何に玄賓僧都の跡を慕っていたかが分かるのである。玄賓僧都は、弘仁(こうにん)二年(818)に享年八十余歳にして遷化(せんげ)した。俗姓は弓削(ゆげ)氏、興福寺の宣教に法相宗を学んだ。大僧都に任ぜられるも辞退して隠棲された経緯は、すでに述べた通りである。
『発心集』に載せられたこれらの逸話からでも、われわれは多くのことを読み取ることができるであろう。
まず第一に、玄賓僧都のように、学徳兼備の名僧でありながら名利を厭(いと)い離れた人こそが、真に万民から敬慕されたという事実である。
そのことはかえって、今日と同様、当時も大多数の僧侶は、出世間の修行をする身であるにもかかわらず、足実地を踏んだ着実な宗教的体験を欠いたまま、名利の俗念にがんじがらめになっていたということを意味する。
第二には、当時の桓武天皇(周知の通り、天皇は平安京に遷都されて、京の千二百年の都の基を造られた)が、玄賓僧都のような真に高徳の僧を崇敬されたのは、天変地異や政情不安の只中にあっても、天皇が確かな法の眼を具えておられた証拠であろう。
そして第三に、鴨長明を初めとして、後世の多くの心ある人々もまた、玄賓僧都の気高い行跡を敬慕した。謡曲の「三輪」は、高徳の僧都に巡り合って、三輪の神ですら仏道に結縁できたことを悦んだという筋書きになっている。
日本最古の幹線道路といわれる奈良「山辺(やまのべ)の道」の三輪山付近には、僧都がその昔ささやかな庵を結ばれた旧跡「玄賓庵」(寺の読みでは「げんびあん」)が、往時を偲ばせるようにひっそりと佇んでいる。その辺りの道は、今にも玄賓僧都が姿を現わされそうな趣が感じられる。
・「名僧列伝」トップへ..
・このページのトップに戻る..
- 発心:仏道を究めようという切なる願いを起こすこと。 [↩]