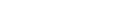「東嶺禅師の入道要訣」2019年4月【No.190】
臨済宗中興の白隠慧鶴禅師第一の高弟である東嶺円慈禅師(享保六年—寛政四年、1721−1792)の『快馬鞭』という著作の中に、「入道要訣」という重要な一文があります。「凡夫の境地から仏の境地に到るにはどのように心がければ良いか」を説かれたものです。あまりご覧になった方も少ないと思いますので、坐禅弁道を志す人のためにご紹介したいと思います。ここでは余計な解説を加えることなく、逐語訳してご紹介することに致しましょう。
* * *
入道要訣(仏の道に入るための奥義)
禅宗の凡夫の境地から直ちに仏の境地に登るには、五つの料簡がある。一、同性の義、二、異塗の義、三、憤励の義、四、進修の義、五、帰本の義である。これが重要な道筋である。
一、同性の義
人々が具足する本性と、三世(過去・現在・未来)の諸仏の本性と、何ら変わりがない。有難さや荘厳さも同じである。光明も同じように放っており、智慧や神通も同様である。
例えば、太陽の光が山河大地を照らしてあますところが無いようなものである。汚い糞土の上にも、貴重なものにも、同じように明るく照らしている。ところが、盲人(普通の凡夫)は、その光の中にいながら、見ることも知ることもない。まことに哀れなことである。
二、異塗の義(「塗」とはこの場合「道」という意味)
本性は諸仏と衆生とは同体で何ら変わりはないが、その心の目指すところが違っているのである。仏は内に向かって、本心を照らされるのに対して、衆生は外に向かって、さまざまな対象に心を散乱させる。
したがって、物を愛しては貪欲(むさぼり)となり、憎む者に対しては瞋恚(怒り)を起し、その思いが凝り固まってとなる。この貪・瞋・癡の三毒の性質に迷いくらまされて、本心をも失うことになる。
貪欲が深い者は餓鬼となり、瞋恚が深い者は修羅となり、愚癡が深い者は畜生となり、三毒すべてを持っている者は、地獄に堕ちて、さまざまな苦しみを受ける。これを「四悪趣」というが、恐るべき極みである。
貪・瞋・癡があっても、自ら戒めて三毒に身を任せてほしいままに振る舞わないのが、人間であり、生まれ変わり死に変わりしてもこの身を失うことがない。
貪・瞋・癡がようやく静まって、自ら戒めなくても三毒に身を任せることのない者は、天上に生まれる。これを「六欲天」という。
三毒の性がなくなって、と智慧の徳はあっても、禅定に定愛(執着)し、瞋・癡の習いがまだ残っているのは、色天十八種の中に生まれたのである。
定愛がすでに尽きてはいるものの、未だ仏の知見を開かないのは、「無色界の四天」という。声聞・縁覚の修行者は、この天に生きる者である。
先の「四悪趣」に「人天」を加えれば、「六道」となる。声聞・縁覚と菩薩と仏とを加えれば、すなわち十界となる。
およそ六道のうちにいる間は、たとえ人間界や天上界(人天)の楽しみを受けることがあっても、皆苦しみの種である。どうしてかといえば、貪・瞋・癡の煩悩の深い心をもって、この世界を作り上げ、この身を感じ出したのであるからである。
そうならば、この業である煩悩を滅しなければ、解脱はできない。この六趣の苦海を解脱しなければ、真の安楽ではない。
この苦海を解脱しようと思うならば、先ず無常を観ずるべきである。生ある者は必ず死ぬ。若いからといって当てにはならぬ。強い者も危うい。富貴な者も衰える。尊貴な者もいつまでもそのままでおれるものではない。長寿も八十年を過ぎることは稀である。
したがって、この世は無常であり、楽しむべきことは何も無い。貧しければ無いことに苦しみ、富める者は有ることに苦しみ、身分の高い者は高いことに苦しみ、卑賎の者は卑賎であることに苦しみ、衣食に苦しみ、妻子に苦しみ、財宝に苦しみ、位官に苦しむ。
とにかく、煩悩の性を滅ぼして解脱の道に到るのでなければ、国王大臣・諸天神仙の位に昇ることがあっても、電光や朝露のごとくはかないもので、ただしばらくの間そうあるだけである。
縁が合すれば了々としてあるとはいえ、縁が散じてしまうと空である。父母の縁を借りてこの身を得た。地の縁をもって皮肉筋骨ができた。水の縁をもって唾・涕・膿・血ができ、火の縁をもって暖和柔順である。風の縁をもって呼吸をする。
この四つの縁がたちまち尽きてしまえば、身体が冷たくなり息も絶え果てて、我というものはない。そのときこの身は実際の我ではない。ただ仮の宿に過ぎぬ。どうしてこの仮の宿に貪著して、永劫の事実を顧みようとしないのか。
この無常・苦・空・無我の四波羅蜜を観じて、菩提の道を求めるのを、声聞四諦の法という。これは諸仏が入道する際の最初の肝要な入り口である。
また縁覚の十二因縁というのは、本心が暗いためにさまざまな業を作るが、これは無明と行との二つである。業が積もって習性となる。
その父母に縁を頂いて胎内に宿る。これが識と名色となり、体形が出来上がって六根がようやく成るのを六処という。
出生し、未だ好き嫌いを少しもわきまえないのを触という。
三歳になってからは、早くも花や味を悦び、美しい色を愛する、これを受という。
十歳以後、財色を求める心があるのを愛という。
十五、六歳を過ぎては、しきりに貪著するのを取という。
二十歳より盛んに業を作って、罪を恐れないのを有という。
この業を作り罪を重ねるうちに、未来に生まれる処が善悪ともに定まるのを生という。
一生このような業のみを作って、老い衰えて死ぬ、というのを人間十二因縁という。縁覚はこのことを観じて、煩悩を尽くして菩提に入る。これもみな諸仏入道の方便である。
無明の暗い心を悟って、その真実の本性を見得すれば、無明即仏性となり、行即道となり、識即智徳となる。その場合には、十二因縁がみな正法に随順して、ついに解脱という大いなる成果に到ることになる。
また菩薩の六波羅蜜というのは、布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧のことである。
先に述べた声聞・縁覚の二門の修行は、ただ自分一人を利益するのみで、他人を利するという方法がない。
菩薩は自利の仏道修行をしつつも、また他を教化する行を兼備しているものである。
法のために財を惜しまず、上は師長(尊者・年長者)に供養し、下は貧しい人たちに施しを与えるのは、財施である。自己の智徳のできるかぎり、人のために説法・教化するのは、法施である。この二つの施しをもってあまねく衆生に施す。これを布施波羅蜜とする。
心の内に道心を護持し、十重四十八軽の戒行を修する。これを戒波羅蜜とする。
道理を観ずることを忍受し、褒められたりそしられたりしても、一向に動ずることなく、一念の怒り・恨みも起さない。これを忍辱波羅蜜とする。
自利利他の大いなる実践において、日々に増進し、怠慢を誡め励み進むのを、精進波羅蜜とする。
坐禅工夫を専一に心がけ、一切の妄想を離れるのを禅定波羅蜜とする。
教理を究め、仏の意を察して、さまざまな迷いの情を打破して目覚めるのを、智慧波羅蜜とする。
以上が菩薩の六波羅蜜と言われるものである。この声聞・縁覚・菩薩の修行を三蔵ともいい、三乗ともいい、諸仏成道の方便にして、万古不易の(未来永劫変わることなき)法である。
一仏乗の学者が、これを小乗三蔵の法であるとして痛く退けるのは、小乗の偏見を砕いて大乗の妙理を開悟させんがためである。大乗の妙理を信解すれば、三乗の修行門はみな大乗門を補佐する助けとなる。
例えば、臣民・奴婢は君主よりも劣るとはいえ、もし彼らを捨ててしまえば、君主の威徳を失うようなものである。臣民が多いゆえに君主も尊い。小乗を円満具足するがゆえに、大乗の道も広大となる。三世の諸仏・歴代の祖師も、みな三乗の修行門から法成就に到られたのである。
いま心ある人は思うべきである。四悪趣の苦患(苦しみわずらい)はどれも恐ろしいものである。人天の福徳も頼りにはならぬものである。ともかくも声聞の四諦こそ、おのおののよき修行である。
この世の中はみな苦である。無常であって心細い住み家である。すべてはついに空に帰する。この身体すら我が物ではない。まして妻子・珍宝および王位・眷属・牛馬などが我が物でないことはいうまでもない(苦・無常・空・無我)。
死ぬ時には独りで死んで行かねばならぬ。誰が自分に伴ってくれるであろうか。何物を死んで行く身に携え持つことができようか。
今の他人は前生の親子・夫婦である。今の親子・夫婦は来生の他人である。今の牛馬・魚鳥は前生の眷属である。今の眷属は来生の牛馬・魚鳥である。業に引かれ縁に随って、どのような生を受け、どのような身となるかも分からない。
そうであるから、今の親子・夫婦のような極めて親しい人であっても、(死んで)別れてしまい、どの国に生まれ、何になっているかも知れない。
骨肉の親しさもただ五十年の間である。例えば、一夜の宿りの友であるということで深く愛し、その他の人を憎むようなものである。一夜明けて宿を出立すれば、その友は西東に散って、自分は独りで行く。以前に憎んでいた人は、またその夜の友となる。
(それゆえ)ただ頼むべきは菩提であり、求むべきは仏果である。この身は十二因縁をもってできた業障の皮袋である。まず無明の根元を打破せねばならない。根元が破れて枝葉が残っていることはない。
財施・法施をも自分の力に応じて心がけよ。仏の禁戒を守って犯してはならない。物事に耐え忍んで怒りを起してはならない。朝夕仏や神に祈り誓って、励み進んで念々忘れてはならない。暇があれば坐禅せよ。法を聞いて迷いを覚破せよ。これが菩薩の六波羅蜜の法である。
この根本の性は諸仏と同一体ではあるが、仏は内に向かい、衆生は外に走るという一念の誤りから、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上という六趣、声聞・縁覚・菩薩の三乗、それぞれ九つの世界の衆生に分かれたのである。
これを異塗の義というが、その根本に帰れば、また同じように諸仏と同一体である。どうしてそれを願わずにはおれようか。
* * *
以上は「入道要訣」の「一、同性の義、二、異塗の義」までを訳出したものです。が工夫弁道のご参考になれば幸いに存じます。