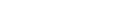「老僧が接木」2014年10月【No.136】
『駿台雑話』という書名を年配の方ならご存知ではないだろうか。小衲も学生時代に、この書が儒者である室鳩巣(万治元年ー享保十九年、1658−1734)によってものされた、江戸時代を通じて屈指の随筆であり、教訓書であることを学んだ覚えがある。学徳兼備の碩学が七十歳の半ば近くになって、程朱(程明道・程伊川と朱子)の学の正当である所以を力説すると共に、当時の世相が浮薄に流れ、純忠質実の風が失われつつあるのを憂えて、古人の勝れた言行を述べた条も数多い。森銑三氏校訂による岩波文庫版は訳註も現代語訳もなく、現代のわれわれにとってはなかなか読みづらいところもあるが、それでも味わって読んでいると、含蓄ある記述が多々散見される。
そのひとつに「老僧が接木」と題する条がある。それによれば、室鳩巣(むろきゅうそう)は幼年の頃に江戸の谷中(やなか)にある真言宗の或る寺院の住職と知り合いになり、たびたびお寺に行って木の実拾いなどをして遊んだらしい。或るときその住職が先住の老僧の時の出来事を話し始めた。それによると、寛永年間のことであろうが、鷹狩りに来た将軍があちこち歩いて見て回った折りに、そのお寺にふと立ち寄ったところ、ちょうど八十歳になる老僧が自分で接木(つぎき)をしているのを見た。「和尚、一体なにをしておるのか」という将軍の問いかけに対して、お供(とも)が遅れて二,三人のお付きの者しかいず、まさか相手が将軍様であるとは思いもよらなかった老僧は、そのまま背中を向けたまま、接木の作業を続行しながら、「接木しておるのだ」とそっけなく答えたところ、将軍は笑いながら、「老僧のその歳でいま接木したからとて、その木が大きくなるまで到底生きられまい。そんなことに心を砕くことなど不要ではないか」というと、老僧は次のように返答した、
「貴方は一体どなたか。そのような心ないことをどうしていわれるのか。よく考えてみられるがよい。今この木を接木しておけば、後の住持の代になればいずれも大きく成長するはずだ。そうすれば林も茂り、寺も何とか生計がたつようになるであろう。わしはお寺のためを考えてやっていることだ。何もわが身一代のことだけを考えているのではない。」それを聞いた将軍は、「老僧が申すことは実にもっともなことだ」と感心したという。そのうち遅れていたお供の者どもが集まってくると、葵の御紋の入った御物がそろってきたので、老僧は「さては将軍様であったか」と恐れをなして奥に入ったが、将軍はその老僧を召し出されて物を与えられたという。
『駿台雑話』に見えるこの逸話から知られるのは、徳川将軍が鷹狩りなどをするのは、ひとつには江戸城の外に出て下々の実情を知るという経験を積むことがあったと思われる。家康公もよく市井の人たちと囲碁をしながら雑談されたそうであるが、それは民衆の真情を知らんがためという目的があったということは、勝海舟が力説している通りである。そして件(くだん)の老僧の率直な一言は、お寺を守る多くの住職の偽らざる気持ちであろう。拝観寺院でもない限り、一般寺院の収入というのは少なく、その割に、いざ何か改修工事などがあると多額の費用が必要となる。それでもなるだけ檀家さんにご負担を掛けないようにと日夜腐心しているのが実情である。
小衲もこの光雲寺に住職として入山してからすでに八年以上が経過したが、色々と改善改修しなければならない箇所が見つかり、予算を工面してひとつひとつこなしていけたのは、ひとえに檀信徒の皆さん方や数多くの尊宿方や篤志家の方々のお力添えの賜物である。いずれの住職も、『駿台雑話』の老僧のように、わが身のためにするのではなく、当該寺院の将来のために努めるが故に、その真意を忖度して多くの方々が支えて頂けるのではないであろうか。自分もまたそうしたご住職を見れば、及ばずながらお力添えをすることになるのではないであろうか。
しかし中にはそうした素直な見方が出来ずに、色々と蔭でとやかく批判する者もえてしているものである。これに関して、小衲は、『痩せ我慢の説』という書物を出版するに際して、「貴殿のことをこのように批判したが、文句があれば申し出てほしい」という福沢諭吉に対して、「行蔵は我に存す、毀誉は他人の主張、我に与(あず)からず我に関せずと存じ候」と断言して何ら問題とはしなかった勝海舟の高邁な風格を想起する。諭吉は、「忠臣は二君に仕えずというのに、海舟は幕臣であったにもかかわらず新政府に出仕するなぞというのは恥知らずである」という旨の批判をしたのである。山岡鉄舟も同様の非難にさらされたといわれるが、海舟や鉄舟はいずれも純忠至誠の心を貫いて自らの信ずるところを貫き通したのである。それと比べれば、諭吉などの人物の小人振りが際立つのである。鉄舟は徳川慶喜公に幕臣として仕えたその至誠心をもって、侍従として明治天皇にお仕えしたが故に、天皇も鉄舟に全幅の信頼を置かれたのであろう。
話は変わるが、小衲が住持する光雲寺は開山が南禅寺と同様に大明国師であり、光雲寺の開創は南禅寺のそれに先立つこと、十一年である。ただ戦国時代の戦乱により荒廃していた光雲寺を現在地の南禅寺北ノ坊町に移してご自分の菩提寺として復興されたのは、後水尾天皇の皇后で、徳川二代将軍秀忠公のご息女であられた東福門院様である。中興の英中玄賢禅師が板倉家に養子に入っておられた関係で、家康公の信任厚かった京都所司代・板倉勝重公の二条城付近にあった屋敷を板倉重矩公が寄進され、歴代の板倉家一族の供養を末代に至るまで依頼された。そして東福門院崩御の後、女院御所から後水尾天皇の御所に通じる渡り廊下が移築されたと言われる。
移築された板倉勝重公の屋敷は現在二百人近くが坐禅可能な仏殿の二倍以上の方丈として古地図に記録されている。光雲寺は地震や火災や台風などの甚大な被害を蒙ったことはないはずであるし、長期間無住になったこともない。しかし江戸時代末期になると老朽化したとの理由で解体されたという。現在まで残っておれば、貴重な建造物として珍重されていたであろうに、まことに残念なことである。小衲の経験からすれば、歴代の住職が努力すれば、後住に引き継ぐ際には自分の入山した当初よりももっと改善して引き継ぐことは決して難事ではないはずである。
その疑問に自分なりの答えを見いだしたのは、宮内庁所蔵の『光雲寺雑記』を長年にわたり研究者の人たちと調べた結果、当時の住職が徳川家ゆかりの寺院ということで、何かにつけて改修費用の寄進を懇願していることを知ったからである。果たして、ともすれば東福門院の菩提寺で三百石の御朱印寺という由緒に安住するということがなかったであろうか。寛永寺や増上寺などの将軍家の菩提寺ならまだしも、徳川家も寄進を再三にわたり懇願されても、容易に点頭しなかったことも無理からぬことであったであろう。小衲のこの憶測が的外れであるとすれば、当時のご住職にお詫びしなければならない。
しかしそれにしても、仏殿や鐘楼や東福門院関係の貴重な寺宝が現代まで伝えられたのは、歴代の住職方の並々ならぬご努力の賜であろう。ちょうど本年は11月21日から12月7日までこの光雲寺で三年振りに京都市観光協会の協賛により「紅葉の特別拝観」が予定されている。お時間のある方はお越し頂き、寺宝を見て往事を偲んで頂ければ幸いである。