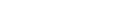山岡鉄舟(一)
海舟・南洲・鉄舟の三人の交友は、無我・至誠の人間関係の好箇の見本であり、そこには日本人のあるべき姿を見て取れるであろう。その中でも剣・禅・書の極意を極めた鉄舟のずば抜けた境涯には、他の二人とも及ばぬものを感じていたようである。
「無我と至誠」の体現者・ 鉄舟
幕末から明治中期まで活躍した山岡鉄舟( 天保七年〜明治二十一年、1836―1888)は剣・禅・書の達人である。その鉄舟の人格の骨(こつ)ともいうべき核心は、何と言っても「無我・至誠」である。この鉄舟の中に、我々は「あるべき日本人の姿」を、また「人間としての真の生き方」を見出したいと思う。勝海舟や西郷南洲らは人格識見ともに第一流の人物と見なされるであろうが、彼らはいずれも鉄舟とは無二の道友であり、その比類なき交わりを通して、鉄舟の人物を高く評価していた。
明治元年(1868)に海舟のもとへ初めて尋ねて来た幕臣の鉄舟は、当時江戸上野の寛永寺大慈院で謹慎中の第十五代将軍徳川慶喜の恭順の意を、駿府の官軍総督府の西郷南洲へ伝える使者の役を担って、その行動の了解を得ようと幕府の要職にあった海舟に面会を求めて来た。
後に鉄舟自身が回顧しているところによれば、そのとき彼は、「国家百万の生霊(江戸市中の住民)に代りて生を捨てるのは、もとより予が欲するところなり」と、「心中青天白日の如く、一点の曇りなき赤心」をもって海舟に面会したと述べている(『鉄舟隋感録』「西郷氏と応接の記」196頁)。
海舟は鉄舟にさぐりを入れた、「貴殿はどういう手立てをもって官軍の陣営中に行くのか」と。鉄舟は、「官軍の陣営に到れば、斬るか縛るかの外はないはずである。そのとき両方の刀を渡して、縛るのであれば縛られ、斬ろうとするならば、自分の思いを一言大総督宮(有栖川宮)へ言上する積りである。もし私のいうことが悪ければ、じきに首を斬ればよい。もし言うことがよければ、この処置を自分に任せて頂きたいというだけである。是非を問わずに、ただ空しく人を殺すという理はない、何の難しいことがありましょうか」と言い切った。我が身を擲って微動だにしない鉄舟の高邁な決意を見て、海舟は俄然同意して鉄舟に一任したのである。
鉄舟は海舟が何かの役に立つと思い同行させた薩摩藩の益満休之助と共に、薩長からなる官軍の総督府に赴いた。鉄舟は豪胆にも官軍の只中を、「朝敵徳川慶喜家来山岡鉄太郎、大総督府へ通る」と大声で叫びながら通り抜けて駿府へ到着し、参謀の西郷吉之助(南洲)と面会することができた。この面談で鉄舟は真情を吐露して主君慶喜の恭順の意を伝えたのであるが、さすがの南洲も、主君のため国家万民のために身命を顧みずに乗り込んできた鉄舟の赤誠には、敵味方の別を超えて心から感動し、慶喜恭順の意を了解するに到るのである。
「本当に無我無私の忠胆なる人」
南洲との江戸城無血開城に関する江戸薩摩屋敷での会見の前日に、海舟は南洲を芝の愛宕山上に誘い出して江戸城下の有様を眺望せしめ、「これを焦土と化しては」と説明した。感無量の体で黙して聞いていた南洲がため息をついて言うには、「さすがは徳川公だけあって、偉い宝をお持ちだ」というから、海舟がどうしたと聞くと、いや山岡さんのことですといったので、海舟がさらに、どんな宝かと反問すると、「いやあの人は、どうのこうのと言葉では尽きぬが、何分にも腑の脱けた人でござる」と言うから、海舟が、どんな風に腑が脱けているかと問うたところ、「いや生命もいらぬ、名もいらぬ、金もいらぬといったような始末に困る人ですが、しかしあんな始末に困る人ならでは、お互いに腹を開けて、共に天下の大事を誓い合う訳には参りません。本当に無我無私の忠胆なる人とは、山岡さんの如き人でしょう」と言って南洲は大いに感嘆したそうである(『鉄舟随感録』222頁、参照)。人口に膾炙(かいしゃ)している「生命も名も金もいらぬ人は始末に困る」云々という南洲の有名な言葉は、このとき鉄舟に関して評した言葉が、南洲の格言として伝えられたものである。
無事役目を果たして帰ってきた鉄舟について、海舟は日記に次のように記している。「山岡氏東帰、駿府にて西郷氏へ面談。君上の御意を達し、かつ総督府の御内書、御処置の箇条書きを乞うて帰れり。ああ、山岡氏沈勇にして、その識高く、よく君上の英意を演説して残す所なし。もっとも以って敬服するにた堪えたり」。さすがの海舟も、鉄舟の私心なき人格と捨て身の働きには心から感服せざるを得なかったのである。
海舟・南洲・鉄舟の三人の交友は、無我・至誠の人間関係の好箇の見本であり、そこには日本人のあるべき姿を見て取れるであろう。その中でも剣・禅・書の極意を極めた鉄舟のずば抜けた境涯には、他の二人とも及ばぬものを感じていたようである。
例えば、海舟は、人の道の根本となる「無我無心」の境地について、「おれも是非この境に達しようと必死になったことがあったが、ついに山岡などのような境にまで達しないで、遺憾ながら今日に至った」(『武士道』144頁)と率直に述べている。
母の至情の教訓
『鉄舟随感録』には、鉄舟自身の貴重な文章と共に、それに対する海舟の評論が併載されている。それを読むと若き鉄舟の心根がどのようなものであったかがはっきりと見て取れる。鉄舟の詳しい生涯は、後に掲げる参考文献を参照されたい。ここではその人格の中核をなす「無我と至誠」の一点に絞って見ていこう。
飛騨高山に生を受けた鉄舟は、武家の子として剣法と書道を習っていたが、その当時を述懐して、鉄舟は「父母の教訓と剣と禅とに志せし事」という注目すべき一文を書き残している(『鉄舟随感録』所収)。
「私は年齢が八、九歳の頃、母が文字の書法を教えてくれた。たまたまその中に忠孝という文字があるのを見た。私はどういう意味かを不審に思い、母にそのいわれを尋ねた。母が言うには、忠と申す文字は、その使う場所によってさまざまな解釈もあるが、この場合は主君に仕える心の正しさをいう。孝と申す文字は、父母に仕えるという意味である。しかし忠と孝とはもともと根本を同じくするもので、人がこの世で生きる上で、必ずこの道理をわきまえなければ、人として生まれた甲斐がないばかりか、申し訳が立たぬものであると、大層情感を込めて話された。
けれども、私は幼年のこととて、それがさほど効能のあるものとは思えなかったが、母の膝によりながら、じっとその顔を眺めてみれば、母は何となく深い心を含んで言われたように見受けられたので、私は幼な心に、母様よ、母様は常にその道を守られているのですか、また私はどうしたらその道を行ない尽くすことが出来るのでしょうかと、何気なく質問したところ、母は何やら心に感じたところがあったようで、はらはらと涙を流しながら言われるには、オー鉄よ鉄よ、母も常にそのように心がけてはいるものの、至らない女であるがために、未だこれといった成果もなく、誠に残念に思っている。そなたは幸いに丈夫な身体に生まれついたのだから、必ず必ずこの母の教えを忘れないでおくれ。忠孝の道は、その意味はなかなか奥深いものがあり、今日そなたに申し聞かせても容易に心に合点するというわけにはいかないでしょう。これからはこの心を持って修行に専念すれば、将来において自然に了解することもあるでしょう。必ず必ず、うち捨ててはなりませぬと、心を尽くして述べられた母の至情の教訓は、この出来事において私の精神にしみ渡ったのである。」
このように鉄舟は述懐しているが、我が子の目前で真情を吐露する母に感応道交して、鉄舟の幼い心にも生涯忘れ得ぬ至誠心が刻印されたのであろう。母たる人の家庭教育がいかに大切かが知られるのであり、鉄舟の母のように、真心や至誠心をもって教育すれば、子供はきっと立派な皆から尊敬される大人に成長するであろう。
すでに十五歳の折りには、「修身二十則」を作って自らの日常の言動を戒め錬磨している。
・次の章「山岡鉄舟(二)」へ..
・このページのトップに戻る..