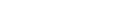徳川家康の仁政(三)
あだ(ひどい仕打ち)を報ずるに恩をもってす
家康公は、大坂の陣が終わって以後、或る夜駿府城において御咄衆(おはなししゅう)1を召し出されて次のように語り出された。(『披沙揀金』525頁)「わしのことは皆も知っての通り、天下戦国の最中に生まれ、年少の頃から明けても暮れても合戦の評議に身心を労し、学問を努めたこともないので、このように無学文盲である。とはいえ、ただ一句の要(かなめ)となる文句を聞き覚えて、これを常に心に忘れることはなかった。三河岡崎に在城していた昔より、天下を統一した今日に至るまで、この一句の道理によって徳川家創業の功を樹立したのである。さて、右の一句というのは、聖賢の教えや仏語の中の一体いずれの書物の内にある、どのような句であると思うか。その方達考えて見よ。」
(我等事、各も存知のごとく天下戦国の最中に生れ、年若き時より明暮合戦の評議までに心身を労し、学問をつとめ候事もなければ、如斯文盲なり。しかれども、只一句の要文を聞覚て、是を常に心にわすれず。参州岡崎に在城せしむかしより、天下一統の今にいたるまで、件の一句の道理に依て、当家創業の功を立たり。扨〔さて〕、右の一句といふは、聖経・賢伝・仏語の中には、いづれの書の内に、いかやうの句にて可有之哉。その方達考へて見よ。)
もとより家康公の信奉されたこの一句が御咄衆に容易に理解されるはずもなかったので、公はついに自らこのように申された。
「ただ今、おのおの方が申したのは、みな四書五経の内にある聖賢の言葉のように思われるので、勿論それらは学問上の肝要な言葉であるには違いない。しかしながら、わしは無学文盲ゆえ、そのようなことはしっかりと聞いたこともない。とはいえ、『あだを報ずるに恩をもってす(ひどい仕打ちを受けても恨むことなく、むしろ有難いと恩に感じる)』という一句を若年の頃より聞き覚え、常に心に忘れず、大事にも小事にもそれが大いに役に立った。したがって、これは取って置きの秘密の言葉ではあるが、今日おのおの方へ相(あい)伝えるぞ。」
(只今、各申見たるは、皆是四書五経の内に出し、聖賢の詞〔ことば〕と聞ゆれば、勿論文道の要文なるべし。然れども、我等は文盲ゆへ、左様の事は聢〔しか〕と聞たる事もなし。乍去〔さりながら〕、『あだを報ずるに恩を以てす』といふ一句を、若年の時より聞覚に、常に心に不忘、大事にも、小事にも、用に立事が多し。されば、大秘文なれども、今日各〔おのおの〕へ相伝するぞ。)
そう言って、家康公はにっこりと微笑まれたそうである。
公は、このようにご自分のことを「無学文盲」と謙遜しておられるが、実は決してそうではない。公が学問(といっても机上の知識ではなく、人格修養としてのそれであるが)を重視されて、機会あるごとに何かと学ばれたことは、すでに述べた通りである。
また、その残された「文書目録」(『徳川家康公御遺品・文書目録』全国東照宮連合会編、参照)を見れば、漢籍に関する公の造詣がよく分かる。
それにしても、ここに引用した逸話に見られる、徳川時代草創期の主従の活き活きしたやり取りは何と素晴らしいことか。まことに人の道を着実に踏み行なう家康公のような主君を頂く家臣達は、その恩恵に浴して充実した日々を送ることが出来たであろう。
秀忠公が、家康公の教示された二句を座右の銘としたこと
前段には後日談がある。家康公が隠居の後、将軍秀忠公近侍の本多正信が、秀忠公名代としてご機嫌伺いにやって来た時のこと、家康公は正信に言われた(同上書、同頁)。「わしは、若い時分、乱世であったので、学問などをする余裕もなかった。そのため、一生無学文盲のままで年を取ってしまった。し<かしながら、『老子』の言葉、『足ることを知って足る者は、常に足る』(いわゆる「知足」)と、『あだを報ずるに恩を以てす』という世間の言葉との二句を、年少の頃より常に忘れることなく肝に銘じて行なってきた。
将軍は、わしとは違い、学問などもあること故、さまざまな善いことをも知っておられるであろうから、この言葉を肝に銘じられよという積もりはない。これはその方に言い聞かせることである」
(我等など、若き時分、世上事いそがはしきころ故、学問などに打懸りて居る事もなし。さるに付、一生文盲にて年をよらせたるなり。去りながら、老子の言葉の由にて、『足る事を知て足る者は、常にたる』といふ古語と、『あだをば恩を以報ずる』といふ世話と、此二句をば、年の若き時分より常にわすれずして受用せしなり。
将軍には、我々とは違ひ、学問なども有之儀なれば、さまざま宜事共をも知て居らるべき間、此語を用ひられよ、といふ事にてはなきぞ。是は其方へいひ聞する儀なり。)
家康公はこのように言われたが、正信がこのことをつぶさに将軍秀忠公に申し上げたところ、将軍は硯(すずり)を取り寄せ、自筆で例の二句を書いて、床の中に張り置かれ、後に金地院崇伝(南禅寺の禅僧)にそれを清書させられた。
将軍自筆の書は、内田平右衛門が所持していたが、三代将軍家光公の御代(みよ)にそれを知られて、平右衛門の子息に命じて江戸城に取り寄せて床にかけられ、裃(かみしも)の正装をされて拝見されたという。
そのとき家光公は、おそらくこの二句を遵守された祖父家康公の心のたけと、家康公に対する崇敬の念を身をもって示された父秀忠公の心中とを、思い量られていたのであろう。
それにしても家康公が種を蒔かれた、聖賢の道に則った仁政が、二代、三代将軍において、かくも見事に結実していたのを見て、先人の気韻(気高い風格)の高さが伺い知れるのである。
まことに、「源深うして流れ遠し」2の感なきを得ない。
僧侶・儒者の堕落を指摘される
家康公がいかに高邁な見識を持っておられたかは、天海僧正・金地院崇伝・林羅山などの歴々を前にして当時の僧侶や儒者を痛烈に批判された、次の言葉からも良く分かる。「今は世も末になり、儒教も仏法も正しい道から逸脱しているように思われる。まず僧は、・・・本当に菩提心を失い、地位や名誉に目がくらみ、私欲をむさぼって私腹を肥やすことばかりに専念している。・・・道の徳があって人を教化・済度する名僧は、万人の内、一人、二人もあるまい。武士・出家・儒者、いずれも真(まこと)の人が絶え果て、偽物のみが横行する時節になったとは、お前達、何も思わぬか。」
(今は世の末になり、儒も仏も、道の正しき事なし、と見へたり。まづ僧は、・・・真実菩提心を失ひ、名聞利養の事を専にす。・・・道徳有て、人を化度する名僧は、万人の内一、二人ならではなし。武士・出家・儒者、何れも真の人絶果て、似せ物の徘徊する時節に成たるとは、何も思はぬか。)
(同上書、560頁)
天海や崇伝や羅山らが、これに対してどのように申し上げたのかは、何も記されていない。おそらく彼らは一言も吐くことが出来なかったのではないか。もし家康公が、現代日本の宗教者・学者・政治家や現代の世相をご覧になれば、一体、何と批判し、何と歎かれるであろうか。
慈悲をもととして人民を救済すべきこと
長たる者は慈悲を根本として人民の愁いを救わねばならぬというのが、家康公の信念であった。公は言われる(同上書、558頁)。「身分の上下・大小に拘らず、物事の道理を良く理解し得ることが、ことに肝要である。しかし、この妙味を知る者は稀である。それ故、鎌倉の頼朝公は、諸国の惣追捕使(そうついぶし)のことをわが物のように心得て、自分だけの栄(は)えある名誉と思われたように見える。その時、天皇の統治はすたれ、世は乱れ、人民が苦しんだ。
(上下・大小に限らず、事の道理を分別し知る事、専要なり。然るに、此味をしる者希なり。然る故、鎌倉頼朝、諸国の惣追捕使3の事、自己の品の様に心得られ、我計〔ばかり〕の栄耀〔えいよう〕と思れしと見えたり。その時、皇統すたれ、世乱れ、人民苦しむ。)
上に立つ者が、乱を治め、民の苦しみを除き、安心させるがための惣追捕使でなければならぬ。わが身の栄えある名誉とばかり思うのは、大いに心得違いである。大体、国家の長たる者は、慈悲をもととして人民の愁いを救わねばならぬ。
いま、自分だけの楽しみと思う故に、民をしいたげ、民の財産(?)をはぎ取り、米穀や財宝を貯え置くのは、国家の主(あるじ)ではなくて、盗賊と言わねばならぬ。天下を失い、国家を滅ぼし、わが身を滅ぼし、先祖に悪名をつけ、一族まで絶え果てた輩は、古今数知れない。それに懲(こ)りることなく、同じような過ちを犯してしまう者が甚だ多い。
(上たる人、乱を治め、民の苦を除き、安堵せしめん為の惣追捕使たるべし。我身の栄耀〔えいよう〕と計〔ばかり〕思ふは、大なるひが事。惣持て国家に長たる者は、慈悲を本とし、人民の愁ひを救ふべし。
今、自己計の楽と思ふ故、諸民を虐〔しいた〕げ、民の肉むらを剥取、米穀・財宝を貯へ置は、国家の主にはあらずして、盗賊と謂べし。天下を失ひ、国家を滅し、身を亡し、先祖に悪名をつけ、一族まで絶果し輩、古今数しらず。是にこりもなく、其跡を踏もの甚多し。)
北条氏は、主君の子孫を絶やし、天下は一旦〔いったん〕は北条氏の思いのままとなった。これは〔結構なことどころか〕大いなる不面目というべきである。それにこのことを歓迎すべき好事だとかん違いし、後の世の者が同じようなことをしようとする。だが、北条氏のように、探り済ますものはない。
また、細川勝元は、己れの祖父の武蔵守頼之(むさしのかみよりゆき)が行なってきた事を学ばずに、北条氏のやり方をまねて、山名持豊(もちとよ)と勢力争いをし、ついに応仁の大乱を起して、日本国中が乱れ公家・武家ともに衰微することになった。
勝元の子の政元は、さらに思い上がりが強かった。将軍義材(よしき)が父義政から位を引き継いだ後、茶の湯をうち捨て、武道を起し、尊氏のやり方を模範にして、畿内近国より次第に悪逆非道の者を退治し、(応仁の乱以後の乱世を)今一度天下統一せんと思い立ち、江州(滋賀)の六角高頼を退治されたので、智のある者はみな足利家の昔に立ち返るべきであると称賛したのであるが、政元は、畠山義豊と心を合わせて、義材公を追い落とし、伊豆の左兵衛佐の幼い子息を擁立して、公方義澄と称した。これは、政元が、天下国家のために主を立てるのではなく、ただ囮(おとり)をこしらえて自分のおごりを究めんがためであった。天罰逃れ難く、政元は家臣の香西元春のために殺されることとなった。
これらはどれもこれも、天下をただわが身ひとりが楽しまんがためのものと思い、人民のことを思わなかったがためである。」
(又細川勝元、己が祖父武蔵守頼之が行跡を学ばずして、北条が跡を追い、山名持豊と威勢を争い、竟に応仁の大乱を起して、四海の中、安所なく公家・武家ともに衰微せり。勝元が子政元、彌〔いよいよ〕奢強く、将軍義材父東山殿の譲を受て、茶湯の事を打捨、武道を起し、尊氏の行跡を取行れ、畿内近国より、そろそろと悪逆の者を退治し、一度天下一統せんと思立、江州の六角高頼を退けられしかば、智ある者は皆足利家の昔に立帰るべしと称顕せしに、政元、畠山義豊と心を合、義材公を追落て、伊豆の左兵衛佐の子息幼少なるを取立て、公方義澄と称す。是は、政元天下国家の為に、主を立るにあらず。只囮鳥〔おとり〕に拵〔こしらえ〕て、自己の奢侈〔しゃし〕を究ん為なり。天の咎〔とが〕、遁れ此等皆々天下を只一己の楽とおもひ、人民を思はざるゆへなり。)
まことに家康公はこの言葉どおりを実践された方である。秀吉の配下におられた折りのこと、秀吉の茶道に関わる者が、「黄金を過分に賜れば、秀吉の飲み給う茶の中に毒を入れましょう」と密かに告げた。しかし、家康公は、これを悦ばれず、「天下は(個々人の欲や計らいによっては如何ともすることのできぬ)神器であり、力をもってことをなしてはならぬ。道に外れたことをして天下を取ろうなどとは思わぬ」と断固これをはねのけられた(同上書、80頁)。
家康公が私利私欲のためではなく、いわば天命により天下統一を果たされた所以が分かるであろう。
人の心得と武士の心得
家康公は、人としての心得はおのれの欲心を捨てることであるとして、次のように言われている(同上書、506頁)。「身分の上下にかかわらず、まず心得るべきことがある。人としての心がある者は、恩を知らなければ人ではないということは、誰でも言うことである。しかしながら、ここに近道があるのを知ってはいない。
主(あるじ)を主とし、親を親とするということは、どのように鈍な主や困った親でも、やれいとしいとか、やれ気の毒なと思って支え育て、何としてでも、主は主の道を立て、親は親の道を立てられるように、寝ても覚めても思うのが、何よりも大切なことである。
ところで、そのように思えるようになるには、自分が嗜(たしな)まずしてはできないことが、勿論そこにある。わずかの欲心を起して万代の恩を忘れ、わが身の栄達を願うような気持ちでは、どうして自分のことが分かり守ることができようか。このような気持ちでするなら、そしるも叱るも、みな欲心である。この気持ちを清算しなければ、褒めるのも愛(いと)しがるのも、みな自分の欲心である。わしはこのことを早くから知っていた。まことに深く味わうべきことである。」
(大より小に至るもで、先可心得事あり。人たる心有るものは、恩を知らずんば、人にあらずといふ事は誰々もいふ事なり。しかれども、是に近道ある事をしらず。
主を主とし、親を親とするといふは、いかなる鈍なる主にても、無理なる親にても、やれいとをしや、やれ笑止や、とそだてて、いかにもして、主は主の道立、親は親の道立やうに、寝ても起ても思ふが第一の事也。
扨〔さて〕、左やうに思ふに付ては、己が嗜ずしてならざる事、勿論其中にあるなり。一端の欲心にて、万代の恩を忘れ、己が身を立る心にては何としてか、我を知て守らんや。此心よりおこれば、そしるも、しかるも、皆欲心なり。此心を弁へざれば、ほむるも、いとしがるも、皆己が欲心なり、といふ事早く知たり。深く可味哉〔あじわうべきかな〕。)
また、武士たる者は「恥なきところを恥じる」べきであるとして、武士の心得について次のように述べられている(同上書、507頁)。
「武士たる者は普通の人とは異なるところがひとつある。恥のないところを恥じるということが、眼目であるということである。その訳は、心の底は他人には分からないが、これが恥なきところである。とはいえ、痕跡(こんせき)を見れば、結局分かってしまうものである。他人が知る知らないに関わろうが、どんな病でも治すことのできる(?)万病円という妙薬は、信を守るという一事に尽きる。これを、それぞれの場合に名を変える時に、主には忠、親には孝、臣には礼、子には慈というが、いずれも同じことを色々呼んでいるだけである。
しかしながら、あちこちに何らかの子細がある。信であると思っても、まことの信であるかどうか知り難い。ここにわしが工夫したことは、とりわけ自慢したいほどのものである。」・・・「これはわしの秘蔵のことである。たって所望ならば言うぞ。」・・・「まことに好きになってよくよく味わえば、まことの信を知ることはその中にあるぞ。」
(士たる者は、常の者にかはる所一つあり。耻なき所を耻る事、眼目の儀なり。其訳は、心底の事は、人はしらざるなり。是無耻所なり。然ども、跡より見れば、何としてもしるるものなり。人の、しるしらざるにかかはるも、星にあたらず車ひくの万病円といふは、信を守る一種の事なり。是を、それぞれによって名を替る時、主には忠、親には孝、臣には礼、子には慈、同体異名なり。
然ども、所々に一種の子細あり。信じゃとおもふても、まことの信やらん、知がたし。爰〔ここ〕に我工夫し付たる事、殊の外自慢なり。・・・是我秘蔵の事なり。達て所望なればいふぞ。・・・誠に好に成てひたと味へば、真の信を知る事、其中にあるぞ。)
「天下は慈悲ぞ」
これまで、儒者の林述斎の手になる家康公逸話集『披沙揀金』と、『松永道斎聞書』(別名『東照宮御遺訓』)とをもとにして、家康公の仁政と、それを可能にした「花も実もある家康公」(太閤秀吉の言葉、『披沙揀金』319頁)の大器量の人柄をご紹介してきたが、以上の逸話を読まれただけでも、家康公の偉大さを称揚せんとする試みが、決して溢美の言でないのがお分かり頂けたと思う。古来の施政者は、唐の太宗の『貞観政要』を帝王学や治政の手本として学んだが、われわれ日本人にとっては、家康公に関するこれらの書は、まさにそれに取って代わるべき重要なものである。政治家のみならず、万人が読んで以て自らを反省修養すべき無類の法材といってよい。まことに、『松永道斎聞書』の「序」にあるように、「心術の秘訣」であり「修身の捷径〔しょうけい〕」である。
家康公が戦国の世を経て天下太平の世を招来された功績は、まことに甚大なるものがあるが、それは、「周公の道、孔子の教え(聖賢の教え)こそが、人として行なうべき道」(『披沙揀金』534頁)であるとして、先賢の教えに従ってわが身を修養してこられた賜物である。
家康公が人生の最後に申された言葉は、竹千代君(後の三代将軍家光公)に対する次の言葉である。
「その方は天下の主(あるじ)なるぞ。天下は慈悲ぞ。」
(同上書、545頁)
この「天下は慈悲ぞ」の一句こそは、まさに家康公のご生涯を貫く一句であると思われる。世界的混迷と乱世の時代に、家康公のこのような高邁な心と生き方を全世界に顕彰して、東洋聖賢の道をよみがえらせ、何とか世界平和と個々人の心の平安をもたらしたいものである。
参考文献
- 『披沙揀金』(全国東照宮連合会刊)
- 『松永道斎聞書』(別名、『東照宮御遺訓』)(久能山東照宮刊)
- 『徳川家康公御遺品・文書目録』(全国東照宮連合会刊)
- 『徳川家康公』(全国東照宮連合会刊)
- 『徳川家康公伝』(中村孝也著、東照宮社務所刊)
・次の章「名僧列伝」へ..
・このページのトップに戻る..