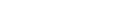徳川家康の仁政(二)
家康公の人望・人徳
家康公は、「栴檀(せんだん)は双葉より芳し」の喩えの如く、年少の頃から聡明であった。十六歳の公の慎み深い態度を見て、すでに今川義元はその大成を予見したという(『披沙揀金』17頁)。公は義元に受けた厚恩を終生忘れず、その塚(墓)の前を通る際にはいつも恭(うやうや)しくして、乗り物から下りられた。義元の長子の氏真(うじざね)が、武運つたなく遂に徳川家に御家人として召し抱えられるようになった後でも、氏真に対面した時には必ず慇懃(いんぎん)に挨拶されたという(同上書、61頁)。
「恭敬(きょうけい)」(慎み敬うこと)こそが、家康公の円熟の境涯が外に顕れた生活態度である。大御所となってからもいささかも礼儀に欠くことなくうやうやしく、威丈高(いたけだか)な思い上がった振る舞いは決してすることはなかった。
公は家臣の「忠信」ということについて、次のように述べておられる。
「臆病な者は必ずがさつで思い上がりが強いものである。思い上がりが強い者は、主君よりもおのれの威を振う者である。真実に忠信である者は、禄高が多くなり身分が高くなるほど主君の恩を深く思う故に、いかなる身分の人に対しても和(なご)やかで慈悲深く、自分の位よりもわが身も言葉遣いも謙虚であるが、これを真実の忠信というぞ。」
(臆病なる者は必がさつにして奢強きものなり。奢強き者は主よりも己が威を振ふ者なり。誠に忠信の者は、大身高位になるほど主の恩を深く思う故に大小上下を撰ばず、人に対するに和らかにして慈悲深く、位より身をも詞〔ことば〕をも引下るを誠の忠信と云ぞ。)(『松永道斎聞書』61頁)
功なり名を遂げ天下統一を果たした後の家康公の人望・人徳を物語る逸話は、それこそ枚挙に暇(いとま)がない。六百頁以上ある『披沙揀金』全編がことごとくこれ珠玉の逸話集である。
今はその中から、大器量で慈悲に溢れた公の人柄を顕わす幾つかの逸話を取り上げてご紹介したい。
武田勝頼の首級に対する信長の態度との相違
天正十年(1582)に武田信玄の子息の勝頼が、織田・徳川連合軍に敗れて自害して果て、その首が信長と家康公のところに相次いで送られてきた時のことである(『披沙揀金』72頁)。信長はそれを見て、「その方の父の信玄は、われらに対し種々の道義に反したことや道ならぬことを行なった。その天罰は逃れ難く、その方も身を苦しめて国を失い、今このような姿に成り果てたのだ。最後に至って思い知ったであろう。おのおの方ご覧になるがよい、良い気味ではないか」と言い放ち、勝頼の首を辱(はずかし)めた。
これに対して家康公は、勝頼の首と聞いて、「まずは三方の上に載せよ」と命じ、座っていた床几(しょうぎ)から下りてその首に向かい合い、両手をつき心を込めて丁寧な調子で、「これもひとえに御若気(お若い故の過ち)のためでありましょう」と慰められたという。
この時、織田・徳川両家の家中の者達はこのことを見聞して、徳川家の者は、家康公の礼儀厚い心情に感じ入り、家康公を末頼もしく思い、他方、織田家の者は、信長のようなやり方では何かにつけて危ういと懸念した。その予想が的中して、勝頼滅亡から八十日目にして、果たして信長は京都本能寺で家臣の明智光秀に討たれることとなったのである。
信長が家臣に謀叛を起されたのも、結局人望が欠けていたためでもあろう。片や家康公は、日頃の修養の賜物で人望・人徳があったことが、このひとことからも分かるのである。
諌言した家臣の忠信を尊重されたこと
家康公が浜松城におられた頃、或る夜、本多正信が御前にいた折りのこと、家臣の一人が参上して懐(ふところ)から封書を取り出し、「諫(いまし)め申し上げたいとかねてより思っておりました事がございまして、書き付けたものです」と申し上げた。家康公は大いに悦んで、「それを読んでみよ」と言われ、その家臣が読んだところ、一条読み終わるたびにうなづいて、「もっともなことだ」と感心され、読み終わった時、「汝がわしを諫めてくれようというその志には、感じ入って言葉も出ないほどである。これからも心置きなく諌言(かんげん)することがあれば、申せ。かえすがえすも殊勝である」と繰り返し言われたので、その家臣も「かたじけなく存じます」と申し上げて退出した。
居残っていた正信が、「ただいま諌言申し上げたことは、採用されるべきことではございませぬ」と申し上げると、家康公は大いに顔つきを変えて言われた。
「いやそうではない。自分の過ちは知らないで過ぎてしまうものだが、その上に、国を領し、人を治める身となれば、過ちを告げ知らせ、諌言するものは少なくて、ただへつらって主君の言うことが道義に違っていても、『そうではございませぬ』と言葉を返す人はないものである。諌言を拒んだ人が、国を失い、身を滅ぼし、後世の笑草となったためしは多い。ただいま我を諌言した者は、日ごろ心を尽くし見及んだことについて、諌言しようと書き記し、おりあらば見せようと思っていたその忠義は、何に喩えようもないほどである。採用するしないに関わらず、ただ彼の忠義の心を重んじるのである」
家康公はこう言って、さらに、「ただ、人の主君である者の賞賛すべきは、諌言する家臣である」と言い切っている。(同上書185頁)
敵将武田勝頼の配下の武将の弟を取り立てられたこと
家康公が小宮山又七郎を奉行に取り立てられた際、その経緯をこう語られた。「又七郎、汝はまだ年も若いが、この役職を申し付けたのは他でもない。汝の兄の内膳(ないぜん)が武田勝頼のそば近く奉公していた折り、同輩の告げ口によって勘当蟄居(かんどうちっきょ)の身となった。だが、勝頼最後の場所へ尋ね行って勘当を許され、悦んで主君勝頼の最後の供をしたる志、まことに武士の手本である。
その内膳に子がないので、その立派な行ないを尋ねる者もないのを不憫(ふびん)に思い、弟の汝を呼び出して、一家を立てるのだ。このたびかような役職を申し付けるのも、兄の内膳に対しての儀である。そのことをよくよく心得て少しもわが身の誉れを思わず、兄の内膳のお蔭と思え。」(同上書、200頁)
家康公はまた、太閤秀吉恩顧の家臣が秀頼に背いて徳川方に寝返ったのを、「太閤の恩を受けていながら、恩知らずの不届きもの。憎きやつ」と叱責されたという(同上書、174頁)。
これらから、武士道に適った行為は、たとえ敵方のことであっても心から賞賛し、人の道を踏み外した所業は、たとえわが身の利になることでも厳に退けられたことが分かるのである。
田植えする家臣の姿に涙されたこと
家康公は深い考えがあってたびたび鷹狩りを催されたが、これはまだ岡崎城におられた時のことである。あるとき鷹狩りに出られる途中で、百姓に交じって田植えしている家臣の一人を見つけて呼び寄せられ、その目も当てられぬ質素な身なりを見て、憐れんで次のように言われたという。「主(あるじ)が小身であるから、その方などを初め、家臣の面々に俸禄を加増してやることもできぬ。ありきたりの俸禄では、人馬や武具等を十分に整えることも出来ない。不十分であるから、このように手作業をしてわが身の辛苦をしているのは、まことに不憫(ふびん)である。だが今は身を汚して苦労してでも奉公をしてくれ。主君も家臣も最初に苦労して、あとに楽をするというように心得た方がよいぞ。さあ、早く帰ってかせぐがよい」(同上書、263頁)。
家康公はこう言って涙ぐまれたので、田植えをしていた当の家臣はもとより、お供(とも)の者達もみな、家康公のお心づかいをかたじけなく思い、感涙にむせんだ。
まことに家康公は家臣や民・百姓に至るまで慈悲をかけられたが故に、民衆も公に心から帰依し歓迎したが、その様を、太閤秀吉も、「良将の行く先は民・百姓までなびく」と感嘆したという(同上書、79頁)。
賢人君子は、他人のよいところを手本にするということ
家康公は言われた。「愚人・小人というものは、他人の悪を手本として、誰それはこのようであるが、自分はそれほどではないと言って、悪口を言うのを忌み憚(はばか)ることがない。賢人君子は、他人のよいところを手本として、悪いことを最初から取り上げない。そしてわが身が何としても古(いにしえ)の賢人君子といわれた人には到底及ばないと、慎んで行なうのである。とかく真実に智慧のある人は、わが心を頼んで高慢にはならぬものである。もし頼む人は愚の骨頂である。」
(愚人・小人といふものは、他人の悪を手本として、何某はかやうかやうなり。我はそれほどはなし、といふて、悪をいみはばからぬなり。賢人君子は、他人の能を手本とし、悪敷をば初より取揚ず。何としても、古の賢人君子といはれし人には及ばれず及ばれずと、慎み行なり。とかく智恵のあるほどの人は、我心をたのまざるものなり。若頼む者は、愚の九ツ時分なり。)(同上書、510頁)
また、「他人の心情を思い量るべきである」として、次のようにも言われている。
「自分の妻子や家来までも、その心情を察し、『このように思うであろう』と思い量り、その心根に恥じて心がけねばならぬ。他人が何と思おうが構わぬ、自分は自分のやりたいがままにやるのだと、勝手気ままにふるまう時は、節度を忘れてしまい、あとで必ず人が寄りつかなくなるものである。」
(わが妻子・家来までも、其情を察し、『かくこそ思ふらめ』と思量して、其心根に耻て嗜べし。何とおもふとも、かまはばこそ、我は我次第と、気随に任せてふるまふ時は、放逸になりて、後には必人を取失ふものなり。)(同上)
大将に必要なのは大度量の心
家康公は、信玄や謙信が武門の優れた棟梁(とうりょう)でありながら、何故に天下を取る事が出来なかったのかを、明白に述べられている。それは二人とも大度量の持ち主でなかったからというのである。少し長い文章ではあるが、極めて重要なことが述べられているので、以下に引用してみよう(同上書、522頁)。「一般に大将であろうとする者は、いかなることに処しても大器量(心が広く人を受け容れる度量がある)を心がけ、胸中に余裕があるものである。それほど大義を破るというほどでなければ、それ以外の些細な事には構わぬ方がよい。水があまりにも清ければ魚も棲まず、人があまりにも相手に構い過ぎれば交際する者もいなくなるというではないか。
人を使うには、それぞれの長所を採用して、その他の短所は致し方ないと思い、気にかけないことである。天地自然を見てみるがよい。馬や牛がいて人間のために役立つかと思えば、虎や狼がいて人に危害を加える。薬草も生(は)えれば、毒草も生える。どのように良いものでも、問題があるのではないか。また、悪いことでも、場合によって用いることがあるならば、容易に捨て去るべきではない。」
(惣じて大将たらん者は物毎に付て、大法器量を宗とし、胸中に余地あり。指て大節を破らずんば、外の瑣細なる儀は捨べき事ぞかし。水至て清ければ魚すまず。人至て察すれば、交なしとかや。
人を遣ふには、夫々の善所を用ひ、外の悪きことは、叶はぬ成べしと思ひ、棄べし。天地の間を見よ。馬牛ありて人の用を達すれば、虎狼有て人を害す。薬草を生ずれば、毒草も生ず。いかやうよきものも、あしき所あらんか。悪しき所にも、事に依て用るところあれば、たやすく捨べからず。)
武田信玄が海平頼平・望月幸義を滅ぼし、上杉謙信が長尾義景・同謙忠を討ったことは、すべて疑心を起したが故のことで、再度熟慮しなかったからである。あのように親しい一族にあって、わが身の手足となって働くべき腹心の者達を見捨てたのは、胸中が狭かったがためであろう。
さて、わが父の広忠公の時代には、父が病身であられたが故に、武運はやや衰え気味であった。一族をはじめ譜代の郎党・従者はともに、多くは敵方に加勢し、あるいは事の成り行きを見合い、わしが幼少の頃までは役に立たぬ輩(やから)が多かったが、わしに武運が到来して以来、その者どもがみな随従してくれ軍事に忠義を尽くしてくれた。わしは、(過去のことなぞ気にかけず)そしらぬ振りをしてよく彼らを使ったので、みな手足となってよく働く腹心の部下となって、勇ましい功績を顕わしてくれたのである。」
(武田信玄が海平頼平・望月幸義を亡し、上杉謙信が長尾義景・同謙忠を討し事、皆疑心より起りて、再び思慮をねらず。さしも親しき一族にて、我股肱とも成べき者を捨たる、胸中の狭き故ならん。
されば我父、広忠公の御時、病身に渡らせ給ふにより、武運少衰たり。一族をはじめ譜第の郎従共、多くは敵方に与力し、或は日和を見合、我幼少の頃まで用に立ざる輩多かりしが、我武運時来、皆随従し軍忠を励む。我、そしらぬ躰をし、能つかひしかば、皆股肱となり、勇功を顕はしたり。)
もし、かの信玄や謙信のように、昔年の疑いを抱いたままで、何か言いがかりをつけて討伐していたならば、天下に手を広げた時に、味方も乏しく古くからの家臣も少なかったであろうが、わしはゆったりとして細部には拘泥しない心持ち(汪洋なる胸中)を心がけていたので、虎狼のような危険な者も、牛馬のように手足となって役立ってくれ、毒草のような害を為すはずの者も、かえって薬草のようにわしを助けてくれるようになった。
ただ、武士や足軽を使うには、胸中何らのこだわりなくゆったりしていて、心の物差しを忘却してはならぬ。胸中が狭ければ疑心も多い。疑心があれば人を多く使うことは難しくなるものである。」
(若、彼信玄・謙信のごとく、昔年の疑ひを挟み、事に寄て誅しなば、天下に手をひろげし時、羽翼乏く、旧好すくなかるべきに、我汪洋なる胸中を専としければ、虎狼も牛馬の用をなし、毒草却て薬草となれり。但、士卒を遣ふには、胸中汪洋にして、心の曲尺を忘るべからず。胸中狭ければ、疑心多し。疑心あれば、人を多く遣ひがたし。)
家康公はこのように、大将たる者の心構えを説かれているが、これは何も大将に限らず万人に該当することであろう。われわれも家康公のように、他人の荒探しをするのではなく、自己の胸中を充実させる無上の楽しみに専念したいものである。
・次の章「 徳川家康公の仁政(三)」へ..
・このページのトップに戻る..